開業前の歯科医師のための
新OPセミナー
日吉歯科診療所は、真の患者利益を考えた歯科医療のあり方を追求し続けてきました。
メディカルトリートメントモデル(MTM)やメインテナンスの普及により、一生涯に渡って口腔の健康に寄与できる歯科医師を育成すべく数々のセミナーを行ってまいりました。
卒後間もない若い歯科医師向けには「プレオーラルフィジシャンセミナー」を開催し、全国各地から学生、歯科医師の参加がありました。受講生の多くは理念や哲学に共感できる一方で、具体的に何をどうしたら良いのか分からず、結果的には従来の診療スタイルから脱却することが難しかったように思います。

現在日吉歯科診療所で勤務している私たち自身も、学生時代に受けた熊谷先生のセミナーをきっかけにこの医療を志すようになりました。MTMにおいて必要となる規格性のある資料採得や患者教育の手法など一つひとつをとってみても、知っていることや見聞きしていることとそれを実践できるようになることには大きなギャップがあると日々痛感しています。MTMをシステムとして捉えテクニックや方法論だけに偏ることが論外であることはもちろんですが、確固たる理念を礎にし、それを目の前の患者さん一人一人に対して行えるようになるためのノウハウや技術もまた欠くことができないと感じています。
私たちにとっての一番の理想は、カリエスフリー・ペリオフリーを実現し「KEEP28」が日本において当たり前になることですが、実際に来院される患者さんの多くは治療が必要な歯を抱えていることがほとんどです。こうした患者さんたちに対して将来的な口腔の健康を提供するためには、治療の質を担保しなくてはいけないことも事実です。エビデンスに基づいた診断と質の高い治療技術も、この歯科医療には必要不可欠であるとも言えます。

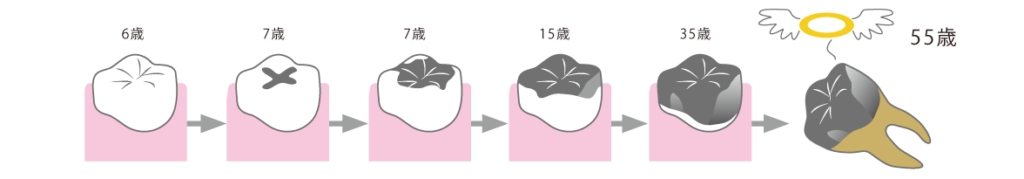

真のOral Physicianであるためには、一般的治療技術に関してもまだまだ学ぶべきことがあると思っています。また逆にOral Physicianで手を付けるべきではない症例、各分野の専門医と連携をとるべき症例についてもその判断が適切にできるような視点を身に付けなくてはなりません。
これまでのプレOPセミナー同様、本当に価値のある歯科医療のあり方として同じ志や理想を共有できる仲間を増やしていきたいという想いを出発点に、より具体的にMTMを実践できるようなトレーニングを追加し、またOral Physicianとして必要となる一般診療のスキルアップまでを含んだ総合的な学びの場をいただきたいと熊谷先生にご相談致しました。
そこで、熊谷崇先生をはじめとし、保存修復・補綴処置では辺見浩一先生、歯内療法では田中利典先生、歯周治療では加藤雄大先生という各分野でご活躍される先生方にご登壇いただくこととなりました。
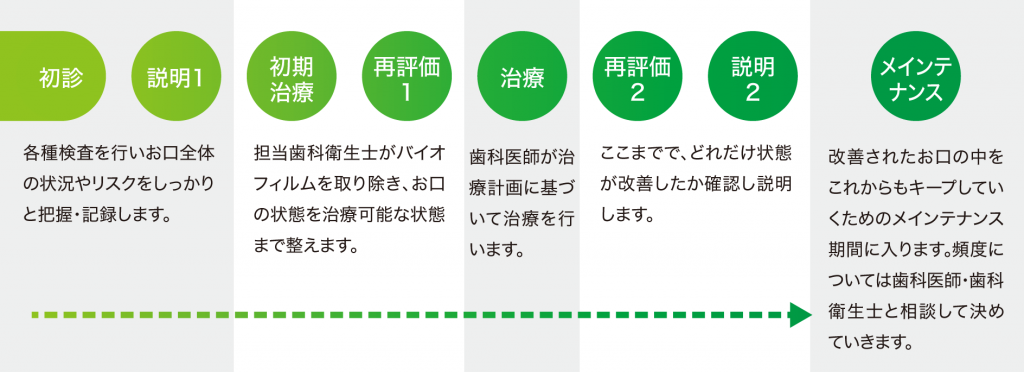
将来を見据えた新しい歯科医療への道に一歩踏み出してみませんか。
熱い想いをもった皆さんと酒田でお会いできることを楽しみにしております。
日吉歯科診療所 石山莉奈・家泉裕香・熊谷崇
活動報告
1期第1回
○感想文
TMの治療の意義、流れなどは現在勤めている予防型の歯科医院でも学んでいますが、諸先生方の講義を聞いてMTM治療の根本にある歯科治療の問題、そこに対して皆さんが提唱されている想いをより一層学ぶことができました。熊谷先生の講義で印象に残っていることは、海外と比較して日本人のハイクラスの人達の口腔内への意識の低さを先生が強調されて仰っていたことです。経済力では世界のトップクラスに立ち、美容や娯楽には当たり前のようにお金をかける国民の口腔内が崩壊していることはよくよく考えるとかなり矛盾することであり、そこには予防歯科の浸透度の低さがあることを改めて実感しました。これは私達予防歯科に積極的に取り組もうとしている歯科医師が業界を根本から変えていく必要があると思いました。一つの治療に対して方法を検討していくような小さな変化ではなく、国民の歯科に対する意識から変えていくことは簡単な道のりではないですが、今回集まった若い先生方の熱心な姿を拝見しこのメンバーと一緒なら大きな変化を起こすことができると実感しました。
MTM治療の進め方や個々の治療のベースは決まったものがあると思いますが、細かな違いや患者さんへの伝え方は先生によっても異なるため意見を交換することで大変勉強になりました。今回は検査方法のコツやメンテナンスで使用する道具などの意見交換がメインとなりましたが、次回以降は患者さんにどのようにお話しして治療を進めているか、つまり心理面でどのように患者さんにアプローチされているかをディスカッションできる時間があると嬉しいです。MTM治療の中では、ただ歯牙に向き合う技術的な治療よりも患者さんのモチベーションアップがより重要になると日常の診療で実感していますが、患者さんによっても生活背景が異なるため、同じ伝え方でも反応が全く違うことが多く治療以前に難しい点だと思っています。今回集まったメンバーは皆さん明るくお話も上手であったため、コミュニケーションの取り方等についても今後教えて頂けると嬉しいです。
私は他の先生方と違った働き方(予防型歯科の医院と総合病院の歯科勤務)をしているため、常時MTM型の治療に向き合っている先生方よりも知識や技術面で劣るところがあり、今回のセミナーにもついていけるか不安がありました。しかし、講義や実技を通して先生方から学ぶことが多々あり、生涯を通して自身の歯を残すことの重要性を再度実感しました。口腔内の問題に苦しんでいる有病者や高齢の方を常にみている立場だからこそ、今後の日本を担う若い人にKEEP28の重要性を伝えていく任務があると強く思うことができました。今後は総合病院での経験例も含めた自分の考えや症例を提示し、2つの全く異なる観点からみている環境を強みにできるように努めていきたいと思います。現地でのセミナーの回数はあと4回と限られていますが、オンラインでのミーティングが発展している時代だからこそ現地のみならずオンラインでの意見交換会なども今後行えると嬉しく思います。
今回のセミナーにはM T Mを実際に取り入れている医院に勤めている身として、よく目にする『予防に取り組んでいます』というホームページで虫歯、歯周病にならないように定期的に通いましょうという言葉には違和感を感じていました。そもそもは病気にならないことを目指すのが予防であり、後出しの予防から先手を打つ予防が本来の姿であると思います。
予防に取り組んでいくためには、絶対に実際に触れ、学ばなければいけないという思いを始めとして参加させていただきました。今までの自分の周りでは、予防歯科、M T Mをというものが共通言語ではなかったので、もっと認知があるべきだ、自身からも概念を伝え広めたいと思いがありました。国民の健康価値観を変えるためにはまず、医療従事者が変わらなければと思います。
参加してまず嬉しかったことは自分が身を置いている環境には間違いがなかったという確信と、似た環境で日々臨床に取り組んでいる先生方と出会えたことです。自分は関西出身で参加者に関西方面の方がいなかったので関西方面ではあまり認知がないのか、それとも取り入れ辛い何かがあるのかという疑問を持ちました。セミナーを受講し終えた後、どういった形で還元できるかを学びの中で探していき自分の課題にしたいと思いました。
熊谷先生の話を聞き、深く印象に残った言葉はやはり『脳のバイオフィルムを取り去る』です。
いかに脳を固定化された概念に惑わされることなく、歯科医療の価値を上げていくようにするか。医療を行う身としてどのように患者さんの健康を守り、社会へ貢献していくことを考える必要があるのか。歯科医療の改革が必要だということを学びました。
人生100年時代、寿命が長くなる中で、治療すればするほど歯を失う未来が待っているということは、医療として大きな矛盾を生んでいます。今までの治療中心から予防中心にシフトすることは必然的であり、取り組まなければいけません。そのためには、シフト出来ない理由、障害を知る必要があります。
そして、国民の歯科へ価値観の変革が重要であることを学びました。人はどうしても目先の利益や損失に目がいき、長い目での投資という見方がなかなか出来ません。それが制度や所得など社会の情勢から仕方ないと割り切ると変革は起こせないと感じました。今ある制度の中でどうするかではなく、どうすれば変えることができるのかへの思考のシフトが必要だと思いました。
明るい未来を築くには埋もれることなく、改革への取り組みをしている人を知り、増やして声を大にしていかなければならないと思いました。治療中心の考え方に染まる前に今回の講義を聞けることを嬉しく思います。
予防を謳う上では、やはり治療の質の担保が必要であることは言うまでもありませんが、若く経験がない状態の今だからこそ治療ファーストの学びではなく予防を行うために学ぶ予防ファーストの学びを得ることが必要だと思います。今回のようなM T Mを始めとした予防歯科を中心に治療の専門家の先生に根拠に基づいた医療を学べるような機会を経て、身に着けることを今後の歯科医師人生においての第一歩としたいと思います。
歯科医師免許を持つことは相応の責務が伴うこと。そして、前に立つことは後ろの人に道を示す責務があるので今回のセミナーを通して自分にできることを学びたいと思いました。
新OPセミナーの第一回、2日間本当にありがとうございました。熊谷崇先生をはじめ、日吉歯科診療所の先生方の講義を少人数で直接拝聴することができ、また実際のMTMに則った診療を見学しながら、規格資料採得の実習まで行っていただき、大変嬉しく思います。診療哲学から、MTMの目的、細かい手順や方法まで学ぶことがたくさんあり、有意義な時間となったことももちろんですが、同じ志を持つ同年代の先生たちにお会いすることができたことも本当に嬉しく思います。日々、臨床と向き合う中で苦戦することばかりですが、石山先生・家泉先生をはじめ、同年代の先生方の患者さんのために向き合う姿を知ることができ、勇気をもらいました。また、一部ではありますが石山先生、家泉先生のそれぞれご自身の専用の部屋で担当患者さんに行っている診療を拝見し、自分の未熟さを痛感し、今後への刺激になりました。それと同時に日本の歯科医療の現状も知りました。日本は巨額の歯科医療費を消費しているのにもかかわらず、他国と比較すると日本人の口腔の健康度や口腔の健康への意識は低いです。こういった事実が歯科医療従事者としてすごく悲しいですし、もどかしいです。これは誰の責任なのか、本当に必要なものに価値が付かない保険制度の責任でもあり、患者さんに正しい知識や教育を行わない歯科医師の責任でもあると思います。わたしも、昔は虫歯になっても歯科医師である父が治してくれるから大丈夫、とブラッシングを適当に行い、今では治療痕が何本もあります。学生時代にPreOPセミナーで熊谷先生の講義を拝聴した際に、これは治っているのではなく詰めているだけなのだと気が付きました。当時、わたしは虫歯を作りたかったわけではありません。ですが、虫歯にならないようにする方法も知らなかったですし、口腔への意識がかなり低かったです。父を責めるわけではありませんが、そのとき正しい知識を教育してもらえていたら…と後悔ばかりが残っています。わたしのように正しい知識を知らずに歯医者に通っている人は大勢いるように思います。きっと患者さんは健康になりたい、これ以上悪くならないようにしたいという思いで歯医者に通っていると思います。そういった患者さんの思いに応えるためには、熊谷先生が長年実践されてきたMTMに則った診療をすることが前提にあると思います。わたしは、患者さんに口腔の健康の価値を伝えていける歯科医師になりたい、という気持ちを今回のセミナーに参加し、再確認することができたと思っています。とはいえ、まだまだできない事の方が多いですし、目の前にある課題を一つ一つこなしていくことで精一杯ですが、今回の新OPセミナーを通して、同世代の先生方と意見を共有しながら、少しでも前に進んでいけたらと思います。残り4回残っていますが、ペリオ・修復・エンドと正しい治療を行うことは予防と同じくらい大切であるとも考えているので、残りのセミナーも実りある時間となるように精一杯取り組んでいきたいと思います。
OPセミナー第1期に参加することが出来、本当に嬉しく思っています。今年度開業医に就職し、セミナーに行かせていただく機会がありましたが、初めて参加したのがPreOPセミナーでした。歯科界には、こんなに素晴らしい考え方を持ち、実践されている先生方がいらっしゃるのだと感銘を受けたことを覚えています。その時から日本の歯科に革命をもたらし、実際に引っ張ってきた熊谷先生の声を直接お聞きしたいと思っていましたが、今回その目標を叶えることが出来ました。実際に熊谷先生にお会いし、お話を聞く中で患者さんに幸せになってほしい、本当に価値ある歯科医療を提供したいという強い熱意をもって仕事をされている姿に、圧倒されました。また、自分自身が今後どのような歯科医師人生を歩みたいのか、ライセンスをもつものとしてやるべき使命は何なのか深く考える場にもなりました。
第一回目はMTMに関する講義、および実際に日吉歯科診療所でおこなっている初期治療の流れを実習形式で参加させていただきました。MTMとは、メインテナンスまでの治療の流れを示したもので自分自身これを行うことで満足している部分がありました。しかし、実際には行うことが目的ではなく、MTMの流れの中でいかに患者さんの意識を変え、行動変容をできるかという点が難しくもありまた私たちが伝えていかなければならないのだと気づかされました。実習は自分の勤めている医院とは異なる点もありましたが、基本的には患者さんに理解を深めてもらうためにも規格性のある資料どりを行い、視覚的に理解をしてもらうというのはとても重要な事なのだと再認識させられました。口腔内写真やレントゲン写真も一見簡単そうに見えますが、実際に取り組んでみると当たり前のことを当たり前にこなせていないところが自分自身の現状です。少しでも妥協してしまえば、患者さんに本当に歯の価値を伝えることが出来ません。自分がつまずくポイントや、上手くいかないこところには何らかの原因があると思います。そこから目をそむけず、明確な目標を立て練習を繰り返さなければならないと思いました。そして脳内バイオフィルムに感染していない卒後すぐの今、歯科医師としての基盤を築く重要な時期だと思いました。治療技術はもちろん歯科診療に向き合う考え方を学ぶことができました 。
今回のセミナーを通じて、本当の意味で患者さんの人生に寄り添い、手を差し伸べられる歯科医師になりたいと思いました。今回セミナーに参加した同年代の先生方も、熱い思いで真剣に歯科について考えている先生方ばかりでした。自分も他の先生方に負けないように、そしてまた同じ志を持つ仲間とともに歯科界を良い方向に導いていける人材になりたいと思いました。明確な強い意思、目的がなければ患者さんを幸せには出来ません。自分自身が想像する歯科医療を自信をもって患者さんに伝えられるようになりたいです。
世界の歯科先進国から多くを学び、日本の歯科医療に改革を起こし続けてきた診療所で、予防医療の真髄を学ぶことができる今回のセミナーは我々若手歯科医師にはこれ以上ないチャンスだと感じています。
OP医院である勤務先にてメディカルトリートメントモデルを学んだつもりではありましたが、その真価を十分に患者さんに発揮できていない…MTMをより一層自身の武器として磨き上げたい…同世代の若手歯科医師と、予防哲学の共有を同時多発的に普及させたい…そういった思いで今回のセミナーに参加させていただきました。日本全国から日吉歯科診療所に同胞が集まり、予防の真髄を学び、各地に戻り活躍していく。これが実現できれば日本の歯科界は良い方向に進む。そのためにも、酒田で精一杯学び、勤務先で誠心誠意患者さんと向き合う。小さな成功体験を積み重ねることで、この半年で私たちは飛躍的に成長できる、第一回のセミナーを受講して、そう確信しました。
プロフェッショナルとして、ブレずに努力をし続けてきた熊谷先生の、チームミーティング酒田Finalを拝聴させていただきました。これまでに熊谷先生がなされてきた功績・苦労に触れて本当に心が熱くなったと同時に、我々若手歯科医師の責務というものがはっきり見えたと思います。チームミーティングでもお話されていた、改革の基本スキル:熱い情熱(warm heart)と冷静な判断(cool head)を常に抱き、日本の歯科医療を改革できる一員になれるよう、今回のセミナーからたくさんのことを学びたいです。
我々若手歯科医師は、わからないこともまだまだあるし、小さな成功体験を積み重ねていくことでしか成長できないので、一人一人の患者さんに真摯に向き合う、これに尽きると感じました。本来であれば険しい道ですが、熊谷先生という先人が作ってくれた予防医療の道を、OPの門を共に叩いた同期と進むことができたら医療人としてこの上なく幸福だと感じました。
日吉歯科さんが掲げる、”命の寿命と歯の寿命を逆転さる=KEEP28”の考え方が素晴らしいと思いました。
熊谷先生の講義の中で、8020が表すことを、手や足の指がかけている写真で表していたスライドがとても印象に残っています。
手や足の指、目などなくなってしまう事はとても大きなハンディキャップとして扱われていますが、歯が1本や2本かけることに対する日本人の意識はとても低いことに改めて驚き衝撃を受けました。
また、8020を国を挙げて主張していること、とても残念だなとおもってしまいました。
日本の歯科のあり方は、今だにかなり遅れていて、口腔内が汚いことに対して何の違和感を抱かない日本人に改めてびっくりしまた。
また、そんな日本を変革しようとお一人で頑張ってきた熊谷先生を改めて尊敬しました。
日本の歯科は、保険制度により、歯科医師の治療に対する意識の低下、患者自身の口腔内に対する意識の低下を招き、質より量の治療を求められているのが現状。自分は、そのような医療を提供したくないと思いました。また、そのような中途半端な医療を提供しないで済むように、患者さんの幸せと健康を一番に願い、そのために決して妥協しない歯科医師になりたいと思いました。
また、熊谷先生のように、日本人の口腔内を変革できる歯科医師の1人になりたいと思いました。
自分だけを変えるのではなく、酒田市のように地域をひっくり返すような取り組みが将来自分にもできるといいなと思いました。
30年以上前の患者さんのデータが今と変わらずあり、現在のデータと比較することができること・30年以上もメンテナンスの来院がある患者がたくさんいること(100歳を超えても自分の歯で食事をとっている患者さんがたくさんいること)本当に感動しました。
また、長期的に患者さんと付き合うことで、家族単位(世代またいで)での来院を可能にし、下顎のAAが萌出した時からアプローチが可能になっていること、本当に素晴らしいことだと思いました。そんな歯科医院がもし自分の地域にあったらな、と強く思いました。
今は、日吉歯科が普通の歯科医院と違うと思われているが、このような素晴らしい歯科医院が普通になっていく世の中を作っていきたいと本気で思いました。
私も、脳みそが感染しないように、今回の5回の講義を体に染み込ませ、妥協した医療を提供しないように、努力していきたいと思いました。
できることを全力でとりくみ、どんどん増やし、できなかったことをそのままにしないでできるようにしていく。そうして患者さんに最適な医療を提供していけるような歯科医師になりたいと思いました。
そのためには、今、MTM・規格写真の重要性をしっかり理解し、自分もそれができるようになり、歯科医・衛生士に教えていけるようにならなければいけないと思いました。
今は、規格写真もまだまだ上手に撮ることができないけれど、勤務先の歯科医・衛生士をも巻き込んで日吉歯科さんのスタッフさんのように精度の高い医療を患者さんに提供できる医院にできるようになれたらいいなと感じました。
また、今後の課題として、自ら成長することがもっとも大事になってくると思いました。最近、日々の診療の忙しさを言い訳に、自己研鑽の時間が少なくなっていることが、ずっと心にひっかかっていました。今回、同じ世代の、歯科医師と話をすることで、自分の弱さや、甘さを思い知りました。
妥協のない治療を患者さんに提供するために、日々できないこと・できることを知り、できないことをなくしていけるよう研鑽を積まなければいけないと思いました。とてもいい刺激をもらいました。
私は、この新OPセミナー当日を本当に楽しみにしていた。理由は、予防歯科を自分自身で行う中で、日本に予防を広めた先駆者の熊谷先生にお会いし、予防歯科や医療哲学について話を聞きたいと思ったからである。研修医の頃から毎日日吉歯科診療所、SATのHPでセミナー案内のチェックをしており、PreOPセミナー東京、おもうしょ勉強会、各OPクリニック見学(松野先生、晝馬先生、畑先生、大島先生など)の活動を続け、掴めたチャンスを大変嬉しく思う。
初回を通じ、熊谷先生の熱量を自分の五感で浴びることができ、改めて予防歯科への意欲を強められた。特に、歯科医療を成熟させる上で最も大切な事は、診療技術でもなく、対人コミュニケーションでもなく、マネージメントや経営能力でもなく、正しい医療哲学をコマの軸とすることであると学んだ。私自身のコマの軸として、ビジョン(健康増進のための行動変容を促し、健康寿命を伸ばす)とミッション(全患者に情報提供し、健康増進のための選択肢を与える)を設定し、これに沿った診療を日々行うこととする。
今回のセミナーで、熊谷先生は「脳のバイオフィルム」というフレーズを強調されていた。保険制度に対する甘え、患者教育不足への言い訳、患者利益の欠如など、歯科医師と患者さんの両者が本気で向かい合っていないすべての理由を、「脳のバイオフィルム」と呼んでいると感じた。予防を基本とし、正しい診療を心がけていたにも関わらず、自分自身がすでに6〜7割も「脳のバイオフィルム」が付着している事が判明した。今回のセミナーで、医療哲学、患者利益を学び(プロフェッショナルケア)、脳のバイオフィルムを落とした日々の診療(ホームケア)を実践したい。ただし、2〜3ヶ月もすると、また前のやり方に戻る可能性があるため、各回のセミナーを初期治療として、徹底的に脳のバイオフィルムを除去していきたい。
今回のセミナーのもう一つの目的は、予防歯科を追求している若手の同志と出会うことであった。今まで若手歯科医師で予防歯科を追求している人にほとんど出会えておらず、各OPクリニックでも課題として挙げられていた。当日を迎えると、私より若い同志が10人もいる事が判明し、心の底から嬉しかった。セミナー終了後も、日々の診療の疑問や、予防中心の組織作りの相談など、心強い仲間となれる事を期待している。また、日吉歯科で鍛えられている2名の若手歯科医師もおり、大変大きな刺激を受けた。資料取り一つを取っても、質と効率を最大化するトレーニングを受けており、思考停止で日々を過ごしていた恐ろしさを覚えた。ただ漫然と数をこなすのではなく、正しい目標設定をして、トレーニングに励むこととする。予防歯科の成功のためには、熟知した歯科医師と、トレーニングされた歯科衛生士が必要となる。熊谷先生が行ってきた事を再現し、予防歯科へ貢献していく。このように我々トップ数%の歯科医師が変わっていく事で、人生100年時代に対する歯科医療の真の価値を創造していきたい。
今回はお忙しい中学びの機会を与えていただき、ありがとうございます。
私自身OPセミナーを受講した先生のもとで勤務させていただいております。疾病を予防するための歯科医療を提供することの重要性は理解しているつもりでしたが、MTMはKEEP 28を達成するための手段であって目的ではないことや、歯科医師というライセンスの重さを理解し、責任を持って歯科医療を全うしていくべきだということを、再認識させられました。また、熊谷先生はひとりひとりの患者様の人生に寄り添いながらも、多角的な視点から歯科医療を見つめ、問題を解決するために、さまざまな職種の方と多くの取り組みを実施していらっしゃいます。診療所内だけでなく、地域や企業・行政に働きかけてKEEP 28を自ら進んで実現しようとするその熱心な姿勢には、感銘を受けました。
一方で、日吉歯科診療所を訪れる前は、歯を失わないための歯科医療を実践されているのかと思っておりました。実際そうなのかもしれませんが、熊谷先生はじめ、他の先生方のご講義を聞いて、KEEP 28、つまり本来ヒトの健康的な口腔内を保つというより前向きな歯科医療であるという印象を受けました。
最近テレビCMでも”予防歯科”という言葉を耳にします。予防というと、”放置しておくと歯は失われるから、それを防ぎましょう!”と言っているようです。もちろん適切なケアを施さなければ歯の喪失のリスクは高くなってしまうでしょうが、私たちが正しい患者教育や治療を行えば、患者様は歯や全身の健康をしっかりと保つことができます。ですから、私たちが取り組んでいく歯科医療は、失わないための保守的なものではなく、健康を保つためのもの、あるいは人生100年時代をより生き生きと過ごすための前向きなものです。患者様の人生に前向きな歯科医療を通して貢献できるということは、私がこれから歯科医師として生きていく上で大きな希望になります。
と同時に、その歯科医療を担っていくことの苦労も身に染みて感じました。資料採得の実習では、私はあまり上手に行うことができず、練習の必要性を強く感じました。また、患者様の意欲を掻き立てるような説明ができる自信もありません。治療技術はもちろんですが、それより前の段階で課題がたくさんあることに焦りや不安も抱きました。
しかし、今回のセミナーでは、同じ世代の仲間たちと情報共有できるという大きな強みがあります。できないことや不安なことを仲間に相談し、改善して前に進んでいくこともできるでしょう。あと4回セミナーが残っていますが、他の受講生の皆さんや登壇されているおふたりの若手勤務医の先生と一緒に切磋琢磨し合い、より患者様の人生に寄り添った歯科医療を患者様に提供できるよう、一生懸命日々の診療に取り組んでいきたいと気持ちを新たにしております。
早速、今回学んだ内容でぜひ取り入れたいと思ったことを勤務先の歯科衛生士に話したところ、とても良い反応を示し、取り入れてもらっています。このセミナーでの学びを最大限に生かすことができるよう、これからも努力して参ります。今後ともよろしくお願い申し上げます。
熊谷先生の講義では、予防歯科の哲学を語っていただきました。講義中の先生の印象は熱い情熱を抱きながらも常に冷静に状況を判断する革命者、という印象を抱きました。それだけ、言葉に重みと説得力のある講義でした。
まず、保険のバイオフィルムにとりつかれた今の日本の歯科の現状についてお話いただきました。改めて芸能人の口元のお写真を見ると、とてもじゃないですが先進国として恥ずかしいレベルだと感じました。日本の歯科保健医療は先進国平均の約4分の1から約10分の1という大変低い料金に設定されているそうです。安すぎるために診療時間は短くなり、治療の質は低下しているのが、今の日本の現状です。今後の歯科会を担う私たち若手が、この今の問題を正しく知ることは、とても大切だと感じました。
その中で熊谷先生が行った様々な取り組みについても教えていただきました。それらは全て、熊谷先生の医療哲学である「患者を思う気持ち」「歯科医療に対する誇りと責任感」「学び続ける意欲」これらを軸にしており、変化したのは周りの環境・情報であるとおっしゃられていました。自分の医療哲学を持つことがどれだけ大切か、熊谷先生のお言葉で深く心に刻まれました。
松本先生のEBDの講義では臨床的な疑問をどのようなサイトを使って、どのように検索すればいいかを教えていただきました。Evidence Basedな知識について「科学的な裏付けがあるため、誰でも同じ結果の確実性の高い診断・治療・メインテナンスに関する知識が持てる。そのため、世界中の人々が同じ知識を共有すれば、日本でものアメリカでもスウェーデンでも同じ診断、治療、メインテナンスを行える。」とありました。日々の診療に追われておろそかにしがちなエビデンスに基づいた臨床検索ですが、自分の中で優先順位を上げる必要があると痛感いたしました。加えて、「Evidence Basedの診療を全てで行おうとすると、膨大な時間と労力がかかってしまう。だから、専門医と協力したチームアプローチが必要。」とも教えていただきました。自分が診療所作りをする際は専門医と協力できる環境づくりを大切にしていこうと思います。
本セミナーは、講師に卒後2年目石山先生・家泉先生もいらっしゃいます。少人数の初期治療実習では、日常診療の悩みや疑問を丁寧にアドバイスしていただきました。実習形式であること、経験年数が近い先生であるからより踏み込んだディスカッションができたことが印象的です。このセミナー唯一無二な点だと思います。
また、全国から集まったOPを目指す同世代の歯科医師と出会えたことも、本セミナーを通じて得た、かけがえのないものです。日々診療していると、どうしてもモチベーションの維持が難しいです。ですが、石山先生・家泉先生をはじめとした、同世代の先生方も、同じ方向を向いて努力していると思うと、自分も成長しようと心に火が付きます。今後は全ての受講生に症例発表の機会が用意されています。トップクラスの先生方に見られるので、緊張感がありますが、そのおかげで日々の診療で妥協しなくなったと感じております。この6か月は全力でMTMに取り組んでいこうと思います。
大変充実した2日間でした。ありがとうございました。
今後の6日間も楽しみにしております。
最近になって少しずつ治療もさせていただけるようになった私は、治療に対して完璧を求められているでしょうか。根管を穿通させられなかったり、う蝕を除去し切れなかった時、まだ半人前だからという言葉に甘える私は反省が足りないと思います。ですから、熊谷先生がおっしゃっていた量より質の歯科医療を追求する流れは卒後2年目の私であっても追求しなくてはいけないのだと気がついた時、身が引き締まる思いがしました。患者さんのイノベーションを起こす前に、まず私の中で変革を起こさなくてはいけません。初診からメインテナンスまで最高の医療を提供できる歯科医師になろうと思いました。
毎日臨床に携わっていると、治療の現場での判断に疑問が生じた時、エビデンスを確かめるよりもその判断に納得しようとする思考に陥りがちです。診療に際しては批判的な視点を持ちなさいと大学で言われてきました。今一度、本棚にある歯内療法や歯周病の入門書を読み解き、次のチャンスに備えようと思います。患者さんの患者教育において個人が行う選択の決定を下す為の材料と自分自身の選択によって行動するための手段を提供するにすぎないという言葉が心に残りました。私は現在、サリバテストの実施と説明をさせていただけるようになりました。パターナリズムにとらわれず、患者さん自身の口腔に対する意識を変える手伝いをしているという、寄り添う姿勢を忘れずに日々の診療にあたりたいです。
MTMを患者さんに伝える際、行動変容に繋げるために、自信を持ってもらいながらモチベーションが上がるように伝える努力が私には必要だと考えました。実践においては苦痛のない資料採得、分かりやすい言葉遣いで自信を持って説明できるように、普段の練習から工夫を凝らしながら熱心に取り組もうと思います。
口腔内写真ではレクチャーがとても分かりやすく、舌の圧排の仕方や鏡の入れ方、鏡を広げる角度、短時間で撮る為の工夫などとても勉強になりました。動作一つ一つに意味があり、患者さんの負担を減らし、正確に撮影する為の気配りを感じました。撮る順番を実習の際はきちんとできませんでしたが、今後撮影する際は患者さんの負担を減らす為にも実践していきます。
チェアサイドで患者さんが座ったままデンタルエックス線写真を撮るという、海外のクリニックのようなシステムはユニークだと思いました。痛くないフィルムの挿入方法、頬粘膜の指での圧排の方法など臨床で実践したいです。
初期治療では、各診療日で話す順番、内容、話し方について教えていただきました。整理してまとめてから臨床に臨もうと思います。
メインテナンスでは使っている道具の一つ一つに特徴があること、使用の順序、その理由についてもご説明をいただきました。動機あるインスツルメンテーションで、低侵襲で確実な診療を心掛けたいと思います。
今回学んだ予防歯科の概念を念頭に置き、毎日の臨床で実践しながら次回のセミナーに備えたいと思います。
今回のセミナーを受けようと思ったきっかけは、令和3年10月に行われたチームミーティングで、石山先生と家泉先生の発表を聞かせて頂いたからです。
MTMを行っている医院に勤めて予防を勉強しても、結局自分で行うことが出来ないのでは意味がないことを感じ、今回のセミナーをきっかけに自分もMTMを自身で実践できるようになりたと考えていました。
実際にセミナーに参加し他の先生方の話を聞いて、MTMの流れの中で治療のみを行っている自分が少数派であることを知り、このままではいけないと思う気持ちがさらに強くなりました。
セミナーの課題で初期治療がありますが、今まで初期治療を行ってこなかった自分がどこまで出来るか不安が多くあります。しかし、石山先生の発表にあった練習方法を参考にしながら自院のスタッフの助けを借りに取り組もうと思います。
今回のセミナーに参加して、熊谷先生の講義から医療倫理の大切さを改めて知ることが出来ました。石山先生 家泉先生からMTMについて講義と実習を受けて初期治療について学びました。様々なことを学びましたが、特に一番印象に残っていることは、日吉歯科診療所の院内見学です。各ユニットにレントゲン撮影機材が用意されていることや、美しく手入れされたお庭など、医院の設備も従来の歯科医院とは異なるものがあり、診療所から空間から一流であることを感じることが出来ました。来院される患者が驚かれるという話も分かりました。しかし、それ以上にその設備を清潔に保っていること、そして診療スペースだけでなく患者から見えない医局や技工室なども整理整頓が行き届いていることは驚きました。診療をする上で、診療スペースの整理整頓が出来ていることは、患者にも伝わる部分でもあり、診療の効率よくなります。整理整頓の大切さは自院の院長から指導を受けていたので、気を付けていましたが、毎日の業務を続けていてどうしても整理整頓をしきれない部分もありました。自分が見学した前日には、矯正治療が行われていたと伺っておりますが、まるで大掃除をした後のような状態でした。今回の見学で本当の整理整頓を知ったような気がします。これから、初診検査を含めたMTMの流れを学んで実践していきますが、まずは、自分のまわりの整理整頓から真似をしようと思いました。
この2日間で色々なことを学びましたが、まずは出来ることから始めて行こうと思っています。今回のセミナーをMTMを始めるきっかけとして、予防の難しさを学んでいきたいと思います。そこで生まれた疑問は、松野先生の抗議で学んだことを参考に解決していきます。人から聞くのではなく自分で調べることの大切さを忘れずにこれからの疑問を一つ一つ解決していきたいです。
松野先生の講義の最後に、熊谷先生の言葉である「医療者としての哲学・倫理観を持ちなさい ライセンスを持つ者としての使命を考えなさい」を聞いて、今の自身の使命は、「患者の口腔内を守る為の知識を学んでいくこと」なのではないかと思いました。残りのセミナーを楽しみに日々の精進を続けていきます。
1期第2回
○感想文
臨床の中での指導、治療を行う際に何を根拠に伝え、行うか。また、根拠を知り、それを踏まえてどう臨床に取り入れるか、初期治療を含めた日々の臨床の中での疑問や指針を、加藤先生講義を受けて学ぶことができました。
診査診断、治療計画、予後判定の重要性を学び、EFPガイドラインは今回の講義で初めて触れる内容でした。
歯周病に関する論文においても、結論等は触れることはありましたがその論文の背景なども教えていただき大変勉強になりました。結論がこうだからという点だけでは押し付けになってしまい必ずしもそうとは言えないということは多々あることを知りました。
論文の背景を学んだ上で、指針を決めることの重要さを学ぶことができました。
診査診断、予後判定は処置毎に行い計画を立てていくこと、歯周病治療の各ステージ毎の根拠に基づいた処置など今後の臨床に対して大変勉強になりました。
予後判定においては、初めに診断したものと初期治療後の反応によっては変化する場合があるため再度評価を行い、治療計画を考える必要があること。これが普段の臨床の中で難しいと感じている点でした。歯の予後について考えることは経験則も必要なものだと思っていました。
しかし、根拠に基づいた明確な基準を設けることで一つの指針として、判断や説明を行うことができる。そうすることで、治療計画における判断をより質の高いものにしていくことは経験の少ない状態でも可能であり習慣化し、経験を積む中でも怠ってはいけないことだと感じました。
そして、予後の評価を初診からメインテナンスの各ステップごとに行い予後を良くするためには何ができるのか、どうアプローチしていくのかを考えることだ大事ということを学び、今回のEFPの歯周治療におけるガイドラインを一つの指針として臨床に落とし込んでいきたいと思いました。
また、初期治療の重要性を知り、現在初期治療を自身で行うことに取り組んでいる中で再度見つめ直していく必要があると感じました。
歯周治療における歯の保存に対しての治療はまだまだ学ぶことが多く、それこそ経験が必要になってきますが、診断無くして治療はないということから、各ステージごとの考え方を学び、技術の研鑽も積んでいきたいと思います。
経験の差をできる限り少なくしていくために若い歯科医師に重要な知識の獲得は今からでもできることであり、根拠を学び間違った梯子をかけないように努めていきたいと思いました。
加藤先生のご講義は全体的にまとまっており、私たちのような若手の歯科医師でも理解しやすいものでした。簡単な内容ではなかったですし、スライドの量を確認した時は正直驚きましたが、終わった後に充実感に満ちた状態で帰路に着くことができました。
歯周病学の研究の変遷については、とても興味深いものでした。私たちはつい最新の論文やガイドラインに目を向けがちですが、”最新”に至るまでの歴史や経緯を紐解いていくことは、その学問を理解する上で必要不可欠だと感じています。その反面、どこから手をつければ良いのかわからない部分もあったため、ご講義の冒頭で歯周病学の変遷をお話いただいて非常に勉強になりました。
また、歯周病の新分類について、自分の診療に落とし込むことができていない側面がありました。具体的には、まだメインテナンスに移行した患者がいないこともあるのか、Gradeの診断項目をどう活かせば良いのかわかっていませんでした。実臨床の中でも、歯石が除去できているか、患者さんが指導した通りにセルフケアをできているか、など小手先の内容ばかりに目を向けていました。しかし、私はこれから長い未来を見つめた上で患者さんと向き合っていきたいので、歯の予後や全身の健康に目を向け、リスクを見極めた上で必要な診査を適切に行う必要があります。また、自分と同じ目を持った歯科衛生士を教育するという重要な責務もあります。今一度自分の診断やリスク評価が適切かを考えて診療していきたいです。
歯周基本治療からメインテナンスの流れまで、ご自身の経験を踏まえながらお話いただきました。私自身、うまくセルフケアを生活に取り入れることのできない患者さんに悩んでおり、私の伝え方が良くないのではないかと、試行錯誤しています。ですが、加藤先生の全額的な治療をされた症例やAxelsson先生のクリニックに訪れていた90歳の患者さんの症例を拝見して、長い人生を自分の歯と共に過ごすことはどれだけ有意義なことだろうと想像すると、自分の携わっている仕事はとても尊いことを実感しました。そして、それらの患者さんの写真に写っていたのは引き締まった歯肉や滑沢な歯面であり、患者さんたちがそれを当たり前に継続できるということは、私たちと同じくらい口腔の健康に重要性を感じており、私たちと同じモチベーションで自分の口腔内と向き合っているということです。先述のように、私はまだメインテナンスに移行した患者さんの治療をしていないので、スライドの写真を見て、感動しました。
そして、治療をするにあたって重要なのがやはり資料採得だと何度も感じました。加藤先生もご自身の症例を丁寧に記録にまとめられていました。中には失敗談もありましたが、それを次に生かすことができるよう、丁寧に自分の治療を振り返る必要があります。今後のステップアップのためにも、今一度資料採得を丁寧におこなっていきたいと思っています。
実臨床でのコツなども、ご自身の体験談を交えながら教えていただき、概念からスキルの部分まで、網羅的に歯周病学についての学びを与えていただきました。加藤先生のように世界的に活躍される先生こそ、資料採得やEBMの実践といった基礎的な部分を怠らずに継続されていると感じました。私自身まだ駆け出しの歯科医師ですが、だからこそ基礎を蔑ろにすることなく、丁寧に一つ一つに取り組んでいきたいです。
また、先生のご講義は話の構成や表現、全てにおいて整理されており、患者さんへの説明もさぞわかりやすいものなのだろうと感じました。日常の臨床の中で、患者さんとのコミュニケーションに対して、とても神経を使っています。先生のご講義やいただいたスライドを思い出しながら、表現の仕方で感銘を受けた部分は盗んでいきたいですし、たくさん試行錯誤して患者さんと信頼関係をしっかりと築いていきたいと思います。
今回は貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。
加藤先生の講義ではEFPのガイドラインに沿って歯周病治療の基本を学びました。海外のガイドラインをしっかり学んだことがなかったため、この講義は非常にありがたかったです。
「プラークが悪いのか、プラーク内の特定の細菌が悪いのか問題」に、自分は今まで振り回されていました。今回丁寧に解説してくださったおかげで、「研究技術の進歩とともに、この論は揺れ続けている。しかし、臨床上我々がするべきことは『バイオフィルムの破壊』である。」という一番大切なことを理解することができました。
また、フェーズ3の講義での、OFDの有用性は想像以上でした。正直、経験がないことも相まって、あまり外科手術に積極的ではありませんでした。ですが、OFDで歯肉縁下の歯石を十分に除去することで、メンテナンス時に何度もSRPをする必要がなくなるのは、長期的に見て非常に価値ある処置と感じました。今回は外科手技のポイントを、動画も併せて教えていただきました。知識の整理と模型練習等を行ったうえで、必要な症例に対し、積極的にOFDを行っていこうと思います。
喫煙患者についての加藤先生のお考えを知れたのも勉強になりました。「切除療法はする。再生療法はしない。歯周病のリスクが高い分、治療がアグレッシブになる」と言われていました。禁煙できない患者さんの、治療計画を考えるときいつも困っていましたが、加藤先生のお言葉で、一つの指標ができました。また喫煙における有害事象をデータとともに学べたため、禁煙指導もやりやすくなりました。電子タバコに関しては、以下のようにお話されていました。「紙タバコも種類によってニコチン含有量が違うが、同じタバコとして指導している。そのため電子タバコだから良い悪いではなく、紙タバコ同様の指導が必要。」今後は電子タバコを含めた禁煙指導を、自信を持ってしっかり患者さんに指導できるのが、うれしく思います。
対面での講義であったため、日々の診療で困っていることを直接加藤先生にお聞きすることができたのも、うれしかったです。悩んでいた症例として、チェアサイドでのプラークコントロールは良好なのにも関わらず、BOPが減少しない患者さんがいました。単に、毎日磨いていても炎症反応が生じやすい方なのか、診療前だけ一生懸命磨いている方なのか、判断がつかず困っていました。そこで加藤先生は、MBIスコアを教えてくださいました。歯周ポケット底からの出血を確認するBOPとは異なり、歯肉溝上皮からの出血を確認することで、4,5日の期間の、プラーク滞積の有無か確認できるスコアです。今後は積極的にMBIスコアを臨床で活用し、患者さんの本当のセルフケアの状態を把握していこうと思います。
歯周治療の基礎をみっちり学ぶことができた充実した1日となりました。ありがとうございました。
加藤先生の講義を受講し、今まで自分自身が患者さんに対して行ってきた治療は本当に正しかったのか考えさせられる場面が多くありました。また、EBMに基づいた治療は答えが明白ですっきりとしていて非常に分かりやすいという印象を受けました。
講義の中で、医療において白黒はっきりさせるのは難しいとおっしゃっていましたが、だからこそEBMに基づいた治療を提供するのが最も効果的な治療であり、また医院ではこうしているから、先生がこう言っていたからといった経験則に基づく治療は今後やめていかなければならないと改めて感じました。だからといってガイドラインをそのまま適応するのではなく、あくまでも意思決定の手段の一つとして用い、患者さんの希望そして自分自身の技量も考慮したうえで使うということをはき違えないようにしなければならないと思いました。
これまでの自分は歯周治療において、歯周組織検査を行い、患者さん教育、行動変容のために染め出しやOHIS等のツールを用い、4mm以上のポケットにSRP、再評価と習慣のように行っていましたが、なぜその行為を行うのか考えずにひたすら掃除屋のようになっていました。しかし、今回のセミナーの機会を得て論文などにふれたことで治療の裏付けになる背景を知ることが出来ました。PMTC、TBIを行うのは過去の先生方の研究で、衛生指導を受け、定期的なメインテナンスに通ったものはう蝕や歯周病の罹患リスクが下がるという研究結果が示されているからであって、SRPのみよりも口腔衛生指導も共に行った群の方が低いプラークコントロールスコアを維持できるという裏付けがあるからだとうことを改めて認識しました。講義の中でSRPに関する論文にも触れました。4分の1顎のSRPとフルマウスSRPでは臨床結果としてどのように異なるのか、日々の臨床の壁でぶつかるような疑問ではありますが立ち止まり調べる行動を怠っていました。ガイドライン、EBMを基にした治療を行うことは患者さんにとって最良の結果をもたらすものであり今後はガイドラインンに立ち返るという癖をつけていこうと思いました。
また、予後判定というのも今後の課題であると感じました。予後判定と聞くと、初診時の検査データをもとに治療計画を立案しその中で1歯ないし1口腔単位の予後を予測するものと捉えていましたが、予後評価とは治療ごとに立て直すものであり。MTMの流れのなかでも何度も練り直し、評価していくものだということが分かりました。
今回のセミナーを通じて、歯周治療はいかに患者さんに動機付けをし、行動変容を行い、それを習慣化できるかということが治療の予後に関わってくると感じました。そのためにも、根拠となる理由が必要であり、一番身近なのがガイドライン、論文であると感じました。4月までの課題として、分からないことにぶつかったときは、ガイドラインに目を通し、気になる点は論文を読んで自分の知識を深めることを実践したいと思います。今回の課題の1つ症例発表では自分の経験則に基づく治療になっていました。患者さんへの情報提供
の中でより患者さんの心に響くような深い話をしていきたいと思います。
加藤先生、若手歯科医師にとって今必要なエッセンスが凝縮された講演をしていただきありがとうございました。MTMの初期治療として歯周基本治療がなぜ必須であるのか、が非常にわかりやすくまとまっていて、今後の初期治療に即座に応用できる知識ばかりでした。
ヨーロッパ歯周病学会のクリニカルガイドラインを一つ一つ論文ベースで紹介していただき、経験則などによるものではなく、根拠がしっかりしているため歯周病の新分類や、McGuireの予後判定など、複雑だと感じていたものが簡潔にまとめられていて、非常に知識の整理に役立ちました。
今回だけで診療の手技が上達したわけではありませんが、今回得られた知識をもとに診療に当たると、一つの症例をより深く広い視点で歯周初期治療を行えると思います。Phaseに分けて歯周治療を行い、基準を満たした治癒が得られなければ次のPhaseへ。というように簡潔に考えられるため、これまで曖昧であった歯周治療におけるゴールがクリアーになりました。
歯周ポケットや歯石、出血の有無、分岐部病変の有無、X線的骨吸収、動揺度などの客観的検査項目から予知性を持って歯周病を評価できるため、治療法の選択も合理的の行えると思います。
これまでは、表面上の数値などの知識は持っていましたが、その数値が何を表しているのか、どのような根拠からきたものなのか、がわからずに診療していましたが、どのような研究でこの治療がrecommendされるのか、といったバックグラウンドが凝縮された講演だったため、診療に自信と根拠を持ってのぞめます。
また、次回の歯周初期治療の課題では、今回の知識をフルに活用し、初期治療及び歯周治療を行えるので、しっかりと規格性のある資料を採得し、根拠のある情報で患者教育を行い、格Phaseに沿って歯周治療を行っていきたいと思います。
とても一度だけの聴講では全てが吸収できるものではないので、レジュメを何周も見返し、わからなかったら調べ、今回のエッセンスを確実に自分のものにしたいと思います。
今回、加藤先生の講義は、EFP治療ガイドラインに沿いながら解説していただけたのでとても分かりやすく、自分の知識を高めることができたと思いました。
臨床経験が浅い私たちにわかりやすく、噛み砕き教えていただきました。
また、加藤先生の経験や失敗談など交え話してくださったのでとても参考になりました。
オペをするとき、私たちが迷わないよう、オペのやり方を動画を交えながら解説してくれてとてもわかりやすかったです。
また、MTMが歯周基本治療としていかに大事なことか改めて学ばせていただきました。
歯周病に罹患した歯の予後評価では、予後評価を繰り返し行うことで制度の高い治療計画を作っていくプロセスを知りとても参考になりました。
当院でもMcGuire先生の予後判定を取り入れていますが、治療後のSOTのタイミングで患者さんと共有することで今後のメンテナンスの意義などを認識してもらうツールのように活用していました。また、治療計画を立てる時も、頭の中では、Good・Fair・Poorに分けて治療計画を立てているつもりだったけど、実際に、書いて、治療を進めながら、何度も繰り返し予後判定をしていなかったので、今後自分の治療計画の精度を上げていくためにも取り入れてみたいと思いました。自分は、予後が悪い歯でも、患者さんが嫌がるだろうなとか、自分が頑張れば数日でも残してあげれるんじゃないかなどを考えてしまって、なかなか”抜歯しましょう”と切り出せないところがあり悩んでいました。しかし、この予後判定表を治療計画説明のツールにうまく組み込んであげることで、長期的に安定する口腔内をまわり道せず作ることが可能であることに気づきました。今残せる歯を大事に使っていける口腔内にしてあげることが私たちがやるべき本当の治療だと思うので、うまくこのツールを使っていきたいと思いました。
EPPクリニカルガイドラインに基づいた歯周治療の流れでは、縁上・縁下プラークコントロールの重要性を改めて感じました。縁上プラークのコントロールはどうしても患者さんに依存するため、とても難しいことは身に染みています。患者さんの縁上プラークを良好な状態に維持させるために私たちが提供できるもの*知識*モチベーション*技術(一緒に練習する)。ここをうまくできないと、歯科医院に来院する意欲がだんだんなくなってしまうため、MTMにおいてここが一番大事なキーポイントであることを改めて理解しました。このポイントを成長させるには、ただ知識を上げるだけでなく、患者さんとの信頼関係や、術者の人間性などが関わってくるため、本当に難しいと思いました。しかし、難しいことだからこそ、うまくいくと患者さんも術者とても嬉しいし、一緒に成長できることが本当に素晴らしいことだと思いました。
縁下プラークでは、ハンドインスツルメントでのSRPが一番治療成果が良いものだと信じていました。超音波をうまく使ってあげることで治療効果が変わらないのであれば上手に使い分けをしていくことが重要だと思いました。また、SRPにより根が削れてしまっているレントゲンを見た時、自分のSRPは大丈夫か心配になりました。SRPも、もっと根の形態を認識して、負担のない処置ができるようになりたいと思いました。
歯周外科手術では、実際に動画を交えてオペの解説をしてくださったのでとてもわかりやすかったです。実は、3/17に初めてフラップ手術をする機会があり、ドキドキしていたのですが、加藤先生の講義がわかりやすく講義を受けたおかげで少し自信を持って処置ができました。経過を見ていく必要と課題もありますが、手術を無事に終えることができ、多くの学びを得ることができました。ありがとうございました。
加藤先生、終日講義していただき本当にありがとうございました。まだ歯科医師になってから3年しか経っておりませんが、今までの臨床の中で悩んでいたポイントや疑問に思っていた点をわかりやすく、そして明確に教えていただき、本当に有意義な研修となりました。論文をただ読むだけでは意味がなく、いろいろな論文を読んだ上でそれらを頭の中で統合し、その治療方針を臨床の中に落とし込んでいかなければならない、という話が初めに加藤先生から話があり、とても納得致しました。何かわからない事にぶち当たったときに、論文を探して読みますが、その考え方を理解したとしても、経験や技術にばらつきが多い歯科医師が、バックグラウンド・条件・口腔内状況の全く異なる患者さんに落とし込んでいく事は容易ではありませんでした。一つの論文を読み、ただ事実だけを受け取るのではなく、そこにある落とし穴を察知し、疑う部分も必要だと再認識致しました。今回、加藤先生に多くの論文の点と点を緻密に線につなげて教えていただき、本当にわかりやすかったです。
歯周炎にとって、最も重要なことはバイオフィルムの破壊であり、我々歯科医療従事者がすべきことは結局そこにいきつくと思いました。いかに患者さんにバイオフィルムの破壊が重要であることを認識させモチベーションをあげられるか、磨けるような環境を作ってあげられるか、そして私たちが行う初期治療やプロフェッショナルケアがしっかりと行えるかで患者さんの口腔の健康度が決まるのだと思います。まずは、私たちが病因論を正確に把握し、患者さんに伝える責任があると思います。そして、MTMに則った診査を行い、一口腔単位としての診断と1歯1歯に対する診断が必要になります。現在、福田歯科医院でもすべての患者さんに歯周病の新分類とMcGuire先生の予後判定を行っていますが、私自身そこまで深い考察はできていませんでしたし、それを見据えて治療計画やメインテナンスの間隔に落とし込めていなかったので大変勉強になりました。患者それぞれの治療計画を立てていく際に各フェーズごとに1本1本の歯に対して予後判定をしておくことで、その後の対応も明確になり、患者さんへの安心感にもつながると思いました。
また、MIに基づく患者さんとのやりとりについても、学ぶことが多かったです。患者さんの性格や考え方をしっかりと把握し、その患者さんに合わせた情報提供の仕方が必要だということがわかりました。普段の臨床でまだ経験の浅い私たちは、こうやったほうがいいですよ、とただ指導するのではなく、患者さんから信頼を獲得するために論文やエビデンスに沿って説明し、確実な指導をすることも必要と教えていただきました。特にアンビバレンスの考え方はすぐに臨床で活かしていこうと思いました。
他にもさまざまな細かいテクニックや考え方を講義していただき、すぐに臨床で活かしていきたい内容ばかりでした。何か月に1度のメインテナンスでも、プロ―ビング値や出血も見逃さず、診査・診断を確実に行うことで健康を維持していかなければならないですし、衛生士の仕事は本当に価値のある仕事だなとも思いました。
加藤先生の講義は、他では聞くことのできない本当に貴重なご講演で、新OPセミナーに参加させていただき幸せに思います。自分なりに今回の講義をしっかりと咀嚼して活かしていきたいと思います。ありがとうございました。
加藤先生の講義を拝聴し、MTM治療の流れに沿った歯周炎治療の全体像を掴むことができ大変貴重な機会となりました。
今回の講義を通して最も実感したことは、歯周炎治療を行う上ではMTM治療の基本である資料採りが何よりも大切であるということです。歯周炎治療の中ではもちろん検査値の変化も見るべきだとは思いますが、治療が進み歯肉の状態が変化すると写真でもかなり変化が見られるということが先生が講義中に示された写真からもよく分かりました。変化をみるためには初診時から規格に基づいた正確な資料が集まっていることが大前提であり、資料が残っていることで治療の効果に対して術者自身も自信を持つことができ、かつ患者さんにも提供することでお互いの信頼関係を築くことができると思いました。歯周炎治療にはもちろんSRPや外科的な処置の実技的な面も重要にはなりますが、まずは規格に沿った資料をしっかり摂れるように日々の診療で意識したいと思います。
また今回の講義を通して、縁上のバイオフィルムの破壊が歯周炎治療を成功させる上で非常に重要になることを実感しました。縁上の細菌へのアプローチにはブラッシングが重要であり、先生が治療が進む中でも毎回のように染め出しをされていることが非常に印象に残りました。染め出しを行うのを治療の時間に押されて省略してしまっていたことを振り返り反省しました。患者さんを指導する際にも目に見える結果があった方が患者さんのモチベーションアップにも繋がるという先生の言葉を胸に刻み、染め出しをしてバイオフィルムの破壊がされているかしっかり確認しながら治療を進めていこうと思いました。先生の症例の中で、90歳代の患者さんでプラークコントロールが良好な方の歯肉の写真を見てこんなにも引き締まって健康的な状態を高齢者でも実現できることに衝撃を受けました。バイオフィルムさえ破壊されていれば年齢など関係なく、生涯カリエスフリーで健康な歯肉の状態を維持できることが分かり、それが実現できる歯科治療を私も提供したいと思いました。
先生が行っていた治療評価の方法も大変勉強になりました。これまでは初期治療が終了した際に治療計画を立てていましたが、先生は初期治療の前から全顎的な予後評価をされておりまた一度だけではなく治療が進むにあたってその都度予後評価を繰り返し行っていることが衝撃を受けました。先生が仰っていたように予後は治療の経過によってもちろん変化するものであり、初回からある程度個々の歯牙の将来を予測しながら目指すべき道を見通して治療を行うことが大事であることがよく分かりました。患者さんにも個々の歯牙の予後評価を提供しながら初期治療を進めることで、患者さん自身が目標を持って口腔ケアを努められるのではないかと思い私も今後の歯科治療で実践していきたいと思いました。
今回の加藤 雄大先生の講義を受けて一番驚いたことは、講義がとても楽しく、約7時間ある講義がとても短く感じたことです。このような楽しく勉強ができる機会を与えくださった熊谷先生、準備をして下さった家泉先生 石山先生そして、素晴らしい講義をして下さった加藤先生に感謝を伝えたいです。
加藤先生の講義は、病因論の歴史からはじめ、EFPクリニカルガイドラインに則り歯周治療の方法を講義して頂きました。
各パートに論文の内容を解説、臨床に則したまとめ、大学の講義では想像出来なかった「どのように臨床現場で使うか」という流れで進んでいきました。
先生の論文解説は、実際に加藤先生がみた大学の風景を交えた解説があり、作成風景が想像でき、自分でその論文を読んだだけでは気が付くことの出来ないような深いところまで理解できた気がします。各パートでまとめがあり、臨床現場でどのように考えるかを説明して頂けて、今回の講義には、明日から使いたい知識が詰め込まれていました。
これまで、歯周治療の病因論や治療法は理解したつもりになっていましたが、より鮮明に知ることができました。
そして、勉強した内容のまとめ方も参考にしたいと思いました。これまで、自分で読んだ本の内容をノートにまとめてきましたが、臨床現場でどのように使うかを考えてまとめたことがありませんでした。実際に学んだ知識の使い方まで考えてまとめることで、その内容の理解がより深まることを知りました。
この度の講義では、歯周治療以外のことも発見があり、とても楽しく勉強することが出来ました。今日、頂いた加藤先生の講義のプリントは今後の歯科医師人生で何度も読み返すことになると思います。セミナー後も読み直し、更に理解を深めたいです。学んだ内容をこれからの初期治療に活かし、バイオフィルム感染症との戦いに勝てるよう頑張ります。
■受講の目的
①最新のエビデンスを知り、臨床への活かし方を学ぶ
②今自分が行っている考え方・治療手順のズレを把握する
■学べたこと(感想)
知らなかったエビデンスを知ることができた
- EPP Clinical Recommendationの存在・エビデンスレベルとコンセンサスレベルで見える化
- 今まで点と点で知っていたペリオのエビデンスを体型的に学べた
- TBIに関してこれほど多くのエビデンスがあるとは思わなかった
- P急発は普通起こさない→hopelessの歯の延命は本当に患者利益になるのか、良く考える
- 縁下デブライドメントのエビデンスと現実案を理解できた
- ルートプレーニングの限界を学べた
- 抗菌療法について
- 特に耐性菌の発生には厳重注意
- 細菌数のpcr検査をして、不必要な投薬は避けていく
- FOの症例選択基準を学べた(まだ12ケースほどしかしてないため、良く見極めて実行する)
- SPCで大切な考え方、適切な処置・間隔について学べた
加藤先生の思考整理がとても美しかった
- 正直半年コースレベルの内容を、シンプルに1日でまとめられる技術に脱帽した
- プラークvs細菌の変遷について、本質を的確にお話されていた
- 歯周病新分類を、今までで一番分かりやすく解説されていた
- リスクの重みづけという発想を知り、エビデンスに振り回されるのを防げた
- 予後判定を信号の色にされているのは、いつも私が行っているものと同じで、安心できた
- エビデンスでっかちでなく現場の歯科衛生士の努力にも触れられていて、バランスが良かった
- MIは以前勉強して理解不十分だったが、臨床経験が増えた今回復習できて有意義だった
- 縁下デブライドメントの手順の考え方が、低侵襲順で受け入れやすかった
- 信念を貫くと、仕事に自信と誇りを持てると感じた!加藤先生かっこよかったです!
エビデンスに即した知識提供をする
- 患者さんからの質問には、「研究上は〜」と科学的で再現性の高い回答をする
- その上で、「◯◯さんの場合は〜」と患者さんごとに適した回答も自分なりに意見する
- 後輩歯科医師の指導の際、エビデンスが確立しているものはその通りに指導する
- YouTubeでの情報発信では、私見にエビデンスを根拠として活用する
- YouTubeのコメントに大量に質問が来ているため、なるべく科学的な回答を心掛ける
規格生のある資料取りをする
1期第3回
○感想文
辺見先生、大変貴重で実りある講義を本当にありがとうございました。修復に関して、診断から細かいテクニックまで普段の臨床の中で私たちが迷うポイントについて、こんなに明確かつ的確に教えてもらう機会は今までないので、本当に意味のある時間となりました。そして、強く感銘を受けたのは、‘’人生最後の歯科治療にする‘’という言葉でした。日々、診療を行っていく中で時間に追われることや、自分の技術不足・知識不足によりベストな治療を提供できていないと思うことがあります。やはり今、目の前にいる患者さんを治せるのは自分しかいませんし、その患者さんの1本1本の歯に対して責任を持たなければならないと思います。幸い、当院は自由診療専門の歯科医院に移行したことで時間を確保することはできます。環境も整っていますので、あとはいかに自分が手を抜かずに日々勉強を怠らずその患者さんと向き合っていくか、に尽きると思います。今回の講義を聞いてこのことが非常に心に刻まれました。辺見先生のようにレベルの高い知識や技術はありませんが、近い志を持って取り組んでいきたいと思いました。また、責任を持つ一つの方法として、まずできることは、その歯に正確な診断をすることだと思いました。1歯の歯に対しての診断があやふやになってしまうと、その後の治療方針や患者説明に自信が持てずに進んでしまいます。患者さんとのコミュニケーションの中で、ラポールを形成していく手段としてもかかせないものだと思いました。結果として、トラブルを回避でき、お互いにとってメリットを生んでいくと思います。その方法を教えていただけたので、これからは治療する歯に対して常に2つの診断し、患者さんに対する責任、その歯に対する責任を常に持っていかなければいけないと思います。今回の講義では、今まで知らなかったこと、間違って認識していたこと、本当に細かいポイントまでご教示いただきました。う蝕除去に関しては曖昧な部分も多いですし、間接覆髄や直接覆髄の考え方も今まで間違っていたように思います。ですが、今回の講義で自分が理解していたことが、正しかったこと、間違っていたこと、明確化できたことがすごく大きかったです。ラバーダムの実習でも、クオドロンテクニックはハードルが高く、今まで実践したことはありましたが、うまくいったことがなかったので毛嫌いしていましたが、正しい方法を教えていただき実践していきたいです。ラバーダムが習慣化でき、辺見先生の方法をマスターできれば、メリットは本当に大きいと思います。また、苦手な2級窩洞の充填についても、すぐに実践してみたいと思います。1日の講義では本当に物足りないほど、本当に充実した有意義な講義でした。それも、辺見先生がこれまで人一倍患者さんの口腔の健康のために、日々研鑽を積まれているからだと思いました。最後におっしゃっていた、常に勉強をすること、エビデンスに基づいた知識をつけること、症例を作ること、は歯科医師をやっていく上での基盤づくりになっていくと思います。あやふやな診断であやふやな治療をしていたら、あやふやな歯科医師にしかなれないと思います。今回の新OPセミナーに参加し、辺見先生にお会いすることができ、講義を拝聴でき、本当に感謝しております。あとは何度も実践と反省を繰り返していき、今回の講義を無駄にしないよう、励んでいこうと思います。本当にありがとうございました。
前回の加藤先生からは、歯周病から一口腔を守るエッセンスを教示いただいた一方、今回の辺見先生からはカリエスから一歯を守るエッセンスを教示いただきました。歯髄が持つ性質を組織学的に捉え、適切な検査、適切な診断、MIに則った治療の一連のプロセスを非常にわかりやすくご講義いただきました。
特に、経験が浅い我々が、日常でよく遭遇するであろう、「この歯髄炎は可逆性なのか不可逆性なのか」「歯髄診は主観的な側面が大きいため、どこまで信頼して良いのか」「カリエス除去はどこまで追求したらいいのか」という疑問を一気にクリアーにしてくれました。
第一に健全歯質を守るための処置、次に健全歯髄を守るための処置、次に日々痛みなく食事ができるような処置、というように、炎症の程度に応じて介入の程度を決定するというのはMIにおいて非常に重要だと感じました。歯髄のLow Complianceという側面から、歯髄保存が可能だと思っていても不可逆性歯髄炎に陥る可能性もあることを患者に説明することで、患者自ら次のステップ(抜髄)を選ぶ、というスライドには非常に驚きました。現状と、考えられる可能性をしっかり説明し、教育することで、トラブルを避けながら治療ができると思います。
カリエスが象牙質まで進行している時点で、組織学的には健全歯髄ではない、象牙質を触るときは常にジェントルに、という辺見先生の言葉がとても印象に残っています。覆髄をした歯髄の組織切片では、臨床症状なく経過していても、組織学的には炎症性細胞が浸潤していました。深部カリエス除去時には、熱や機械的刺激、プライマーボンディングなどの化学的刺激など、さまざまなストレスで歯髄は炎症を引き起こし、不可逆性歯髄炎や歯髄壊死に陥ってしまうので、常に全力で、できうる最善を尽くして処置を行う必要があります。当院では残念ながら、スプーンエキスカは露髄しそうになったら使用する、というドクターが多いため、辺見先生の講義を聞けなければ私も全てのカリエス除去をタービンで行うドクターになっていたかもしれません。ラウンドバーでは切削速度は早いので、チェアタイムの短縮にはなりますが、MIとはかけ離れています。おそらく、こういったところでも、保険バイオフィルムという問題があると感じました。
今回の講義を受けて、カリエスの除去が早くなったわけでも、ダイレクトボンディングができるようになったわけでもありませんが、自分の治療に責任を持つ、一歯の健康をとことん追求する、という基本的で重要な部分を学びました。修復治療でのラバーダムについても、エラーを限りなく少なくする、ラバーダムをすることでエラーの原因がどこにあるか明確にするという考え方が大事だと思います。普段自分が苦しんでいる歯髄の診断や、隣接面の修復など、先輩ドクターの見様見真似で行っていたところがあったので、根拠と自信を持って診療に向き合えると思います。自分が行う治療は、すべて予防的でなければならない、という信念を常に持ち、日々の診療を行っていきたいと思います。
今回の講義を受けて、日々の臨床の中での疑問点の解決につなげることができました。M T Mを行う臨床のなかで、う蝕をつくらないアプローチと再治療を少なくするアプローチがあり、う蝕に対する治療が必要になることは必ず出てきます。その際、介入をする基準の明確化し、治療後の再発、再治療のない対応が重要になってくると考えます。
浅い経験での普段の臨床において、まだまだ1歯におけるう蝕処置は多くあるなかで、根拠に基づいて治療を行う姿勢でとり組んでいましたが、疑問を持つことが多々ありました。今回の辺見先生の講義ではより根拠に基づいた診断、介入、治療について学ぶことができ、より明確化することができました。
診断がつかずに治療をおこなうことはなく、正確な診査診断のもと適切な治療、対応が必要になります。改めて、1歯におけるより正確な診査診断を学び、今回の講義で治療選択のディシジョンツリーという形の指針を得ることができました。この歯の治療に対してどこまで介入を行うべきか?それは適切な対応なのか?と思うことは、正しく明確な診断が下せていないということがわかりました。その治療が適切なものであったかは、最終的には結果を見ないとわかりませんが、正確な診断をもとに適切とされる治療を行うことは例外を除いてより確立高く、良い結果を残せることから必ず行わなければなりません。
ある程度確立されたエビデンスに基づく治療の指針は経験の浅い今必要になり、普段の迷いをなくせること繋がります。また、診断、治療方針を伝える技術も必要になり、同意がなされていなければトラブルに繋がることも学びました。
う蝕、歯髄の診断から治療法の選択、歯髄を温存するためにより適切なアプローチについて、また、治療法の選択に囚われるあまりそれが患者さんにとって適切な対応であるかどうかも考える必要があることも学ぶことができました。患者さんに治療の説明をし、それが許容できるかどうかが大事であると感じました。
歯髄の診断では可能な限り検査を行い、より正確な診断を下す必要があり、普段の臨床の中でも迷うことがあり、より正確な検査ができていないことがわかりました。
う蝕の除去をどこまで行うかという点でも迷うことがあり、今回学んだ指針をもとに適切な対応を行っていきたいと思います。歯髄の反応を見るために経過を必ず見ることが大切であり、選択が正しかったのか治療の予後を観察することが大切だと感じました。
経験を補うために根拠に基づいた診査、診断、治療を心がけ、それを振り返り経験を積むことでより良い結果を得ることができ、これからの臨床に繋げていきたいと思いました。
実習という形で今回はラバーダムを学びましたが、治療の成果を上げるために必要であり適切な治療法の中で怠ってはならない部分だと考えます。より正確に、気を付けるポイントなどを学び普段の臨床で昇華させていきたいと思います。
今後も浅い臨床経験を補うために治療技術と共に研鑽を積んでいきたいと思います。
非常に楽しく、エキサイティングな講義でした。日常臨床で曖昧になり、良く分かっていなかった点を、丁寧に分かりやすく教えていただきました。大変うれしく思います。診療中、知識不足で処置の判断に悩むことが多くあり、自分が正しいことをしているのか、否か評価できずにずっと苦しんでいました。様々なところで、かいつまんで勉強しても、それぞれの知識を系統立ててうまくまとめることができずに、逆に混乱する日々でした。しかし、辺見先生の授業で、それぞれの治療のコンセプトや達成目的を学びました。ディシジョンツリーのおかげで視覚的にも判断しやすくなり、ようやく頭の整理ができたように感じます。今後は明確な診断基準を持って治療ができそうです。明日からの診療が楽しみでなりません。
無症候性不可逆性歯髄炎という概念は、今まであまり意識していなかったので新鮮でした。今、大丈夫ではなく、これからどうなっていくかの予測。時間軸を持った歯髄診断の大切さを学びました。「お前はもう死んでいる」のフレーズは非常に分かりやすかったです。また、この時間軸の必要性を、患者さんに説明する大切さも感じました。辺見先生は「患者説明力は歯髄保存の1スキル」とおっしゃっていました。「先生の言っていたように痛みがでました。次の治療に進んでください」と患者さんが言ってくれるような治療説明を目標に、それぞれのケースに応じた説明内容を、自分で準備しようと思います。
術前の歯髄の状態でう蝕除去のゴールが変わることも、自分にとっては新鮮で、かつ非常に納得いくものでした。選択的う蝕除去か、非選択う蝕除去か、最初に目的を決めてう蝕除去を行うことで、迷いなく治療できることがうれしいです。
また、辺見先生の受講生を思ってくれるお人柄、お気持ちにも大変感謝しております。質問にも真摯に答えてくださり、誠にありがとうございました。辺見先生のおっしゃられた、若手がすべきこと3つ「①エビデンスの蓄積 ②症例を作る ③メンターを作る」これらにすぐに取り組もうと思います。その中の症例作りの点は、次回のセミナーで発表する機会をいただいており、なんて良いチャンスが巡っているのかと、うれしく思います。この機会を存分に生かし、自分の診療スキルの向上に生かしたいです。次回症例発表が楽しみです。
こんなに素敵な講義を拝聴させていただき誠にありがとうございました。
辺見先生の講義は歯科医師として当たり前のように遭遇しますが、しかし1番の基礎だと私は思っている「修復」に関する内容であり大変勉強になりました。普段は歯科口腔外科で手術等も行っていますが、実は治療の中でも1番好きであり興味もあるのがCRや歯髄保存等のう蝕治療のため今回の講義は本当に前々から楽しみにしておりました。
まずは病態の診査・診断の重要性を教わり、普段カルテなどに“う蝕” や “C” のみ書いていたことを反省しました。やはり歯の症状と根管の状態をどちらもを正確に把握することが次に進むべき手段に間違いなく取り組めると実感し、守るべき歯髄を可能な限り保存(それが最終的には私たちの目指すべきキープ28につながると思います)することを目指してまずは正確な診断ができるように努めたいと思います。
また検査の内容でも、いつも迷っている歯髄電気診と冷温審査の正確性や違いを學ことができ大変参考になりました。どちらが偽陽性、偽陰性が出やすいかという内容を先生も文献をもとに説明して下さり、やはり根本にエビデンスがある中で自分も理解している方が患者さんにも説明する時に迷いなくできることを感じました。先生にご紹介して頂いた文献は自分でも掘り下げて理解を深めようと思います。
また今回、ラバーダムについては実習も取り入れて頂き大変勉強になりました。ラバーをすることにまだ慣れておらず抵抗がある私は時間がかかることを理由に避けていたこともありましたが、患者さんも私もお互いにストレスなく治療を進めかつ感染を防ぎより精密な治療を提供するためには今のうちから当たり前のように取り組めるようにしたいと思います。実習に取り組む中で技術の練習も大切ですが、使いやすい材料や器具を揃えることも重要であることを実感することができました。ラバーだけでもあれだけ種類があることに驚き、また今回使用したラバーは普段使っているものよりも伸びやすく非常に作業が楽でした。患者さんに最高の治療を提供するために器具や材料の模索も医院の先生と相談しながら実践していきたいと思います。
辺見先生からちょっとのコツを色々と教えて頂いたことでこれまで迷っていた部分を明確に理解することができました。今回学んだことを繰り返し練習し、一本でも多くの歯を守ることを常に意識しながら修復の治療に取り組みたいと思います。
今回辺見先生の講義を受講し、臨床に対する考え方がガラッと変わりました。今までも自分の中でのベストの治療を提供できるように、知識や技術の練習はおこなってきましたが、その治療が患者さんにとって最善であったか振り返ると疑問が多く残ります。辺見先生の開業理念の中に「何度もやり直しをしていた歯の治療にピリオドを打つ、人生最後の歯科治療を提供する」というフレーズ」を聞きはっとさせられました。MTMの神髄は、患者さんに行動変容を起こしてもらうというところだと私は考えていますが、その中でも、う蝕や歯周病という既に起こってしまった結果に対してきちんと対処出来る技術も必要であると思います。歯科医師が介入したことでrepeated restoration cycleを回すことがあっては決してならないと強く思いました。
現在行っている実臨床においても、院内のルールで辺縁隆線を超える大きなカリエスであればインレー修復にするように何も考えず処置を行っていました。しかし本来の目的はう蝕を除去していかにきれいに仕上げるのかではなく、修復した後どれだけ患者さんがセルフケアしやすい口腔内にできるかにかかってきます。歯科治療は正解がないとため非常に難しくまた面白い学問だと思います。デンタルエックス線写真や口腔内写真一つとっても、角度や方向が異なるだけで診断は人によって変わってくるかと思います。診断を行うための機材が整っていなければ、そもそも目の前の患者さんを救う土俵にすら立つことができないと思います。答えがないからこそ、治療法を選択する上で鍵となるのは、やはりEBMだと思いました。迷ったときは、なぜそうなるのか根拠に立ち返るくせは今後の歯科医師人生を歩むうえで非常に大事だと感じました。
治療を行う中で、前医で神経をとられたという言い方をされる患者さんが多くいます。神経をとってもらったと肯定的な言い方をされる方に出会ったことはほとんどありません。抜髄や感染根管治療は私たちにとっては、それ以上感染を広げない、歯を守るための処置ではありますが患者さんにとっては良い治療法だと受け取ってもらうことは難しく感じます。
辺見先生が治療を行う際には、患者さんに十分な説明を行うことで、「先生がおっしゃっていた通り次のステップに行く時期かもしれません」と言われるとおっしゃっていました。私も今後患者さんにそのような言葉をかけてもらえるような技術、人間性を身に着けていきたいと感じました。
最後に今回の講義を通じて、保存治療の奥深さを感じました。実際にラバーダムの講義もしていただき、実臨床にすぐに生かせるような内容ばかりでした。今後患者さんに向き合っていくにあたり、診査、診断、患者説明、治療技術は自分のなかで大きな鍵を握るフレーズになります。迷ったときはEBMに立ち返り患者さんに最善の治療をしていきたいです。
私は今回の講義を受けて、3つのことを学ぶことができた。
1つ目は、う蝕治療の診断基準についてである。う蝕感染歯質をSelectiveかNon selectiveのどちらで除去するべきか、様々な論文や各学会のポジションペーパーから迷っていたが、辺見先生のディシジョンツリーを通じて理解することができた。また、診断前の検査として、EPTとcold testの各特徴と感度を学び、上手い使い分けや組み合わせを学べた。さらに、AAEのconsensus conferenceであった通り、歯髄の診断と根尖歯周組織の診断を分けて表示すると、次に処置をどうするべきかが明確になり、とても有益であると感じた。日常臨床でも取り入れるため、深在性う蝕の場合は、必ずカルテに各診断名を書いて、臨床に臨んでいく。
2つ目は、治療手順と使用薬剤ついてである。特に、直接覆髄材としてよく取り上げられていたMTAについて、理解を深められた。作用機序だけでなく、使用タイミングについても初めて知ることばかりだった。講義中も、「水養生のために湿綿球を置く先生がいるが、MTAの場合は不要であり、かえって綿球の毛が付着し非衛生である」とお話されていた。この方法はまさに今の私が行っていることであり、すぐにでも直していく。また、仮封期間もなるべく短くするため、2日以降でレジン充填や裏装へ移行するべきと学んだため、すぐに実行していく。ただし、最も大切なのは、適応症を見分けることであり、徹底した感染の除去を実現しないでは、MTAを使用しても失敗すると学んだ。
3つ目は、治療はテクニックセンシティブであるということだ。いくら理論を学んでも、最後に術者が最も研鑽しなければならないのは技術である。ラバーダムは普段の臨床でも用いていたが、かけ方一つ一つにも細かなチェックポイントがあり、大変参考になった。また、当院では最も安い17円のラバーダムを(自費でも)使用していたが、70円代のニックトーンを試したところ、4倍以上の価値を感じることができた。道具一つ変えるだけで、確実性を高め、無駄な時間を省けるのであれば導入する価値があると考えたため、すぐにでも取り入れない。
最後に余談であるが、北斗の拳から「お前はもう、死んでいる状態」や、外はカリカリ・中はsoftなど、視覚だけでなく聴覚でも理解しやすい工夫がたくさん施され、とても素晴らしい講義だったと感じた。必要あれば講義資料を配ったり、質問になんでも答える姿勢だったりと、歯科医師であり、人格者であると感じさせられた。次回の症例発表は、辺見先生の講義を見習って、診査診断のクオリティだけでなく、受講者にも分かりやすい工夫をたくさん施して臨みたい。
辺見先生の講義を聞いて、今までもやもやしながら臨床を進めていた部分がスッキリしたような気がします。また、質疑応答では、同世代のDr達が、みんな同じようなことに悩んで・苦戦しているんだなと思い少し安心しました。臨床について、なかなか正解がわからず、調べても解決しないことが多々あり、たくさん迷っているのが現状です。そんな中、臨床を突き詰めて行っている辺見先生の講義を聞くことができて、本当によかったと思っています。
カリエスの診断から治療の選択、充填方法まで、本当に細部まで考えた治療をしていて感動しました。そして、それがいかに重要かを学びました。
診断では、当院では電気診のみ行っていてそれを信じて診断を下し、治療を行っていましたが、色々なバイアスがあって正確ではないことを知り、とても驚きました。ケースによって使い分けることが重要であること、早速器具を揃えて実践してみようと思いました。
カリエス除去では、なんとなく自分なりにここまでできたら充填にすすむという基準を持ってやってきましたが、その根拠や証拠などはわからず臨床を行ってきました。今回、カリエス部分の細かい性質や特徴・硬さや染色のされ方など細かく知ることができ、とても勉強になりました。また、完全にう蝕を取りきるか?間接覆髄にするのか?抜髄にするか?リエントリーをするのか?どのくらい期間を開けたらいいのか?などカリエス治療にはわからないことばかりでしたが、う蝕の程度・歯髄の状態の観察や、様々な判断基準が存在し、いかに露髄を避けて感染を除去して完全に接着させた治療できるかがその後の予後にとても重要であるのか改めて知ることができました。
治療に正解はないと思いますが、今回の講義で得られた知識を活用し、辺見先生のように1本1本の歯にこだわった治療ができる歯科医師になりたいと思いました。
ラバーダムの実習では、多数歯の防湿はやったことがなかったのでとても良い経験ができました。また、しっかりとした防湿をするにはちょっとしたコツなどがいること(クランプの適合や結紮など)を教えてもらうことができてよかったです。綺麗に防湿ができたときの気持ちよさがわかりました。ぜひ臨床でも実践してみたいと思いました。最後の、充填方法のスライドでは、ダイレクトボンディングだとは思えない綺麗な充填に圧倒されました。あんなに綺麗な充填を自分もいつかできるようになりたいと心から思いました。解剖学的形態を学び直し、最後に教えていただいた、充填するときのポイントを抑えながら今より綺麗な充填が少しでもできるように明日からの臨床で実践してみたいと思っています。
貴重なご講演本当にありがとうございました。
辺見先生の歯科保存学の講義では、多数歯へのラバーダム防湿方法の実習と講義、歯内療法における歯髄と根尖歯周組織への診断方法から、う蝕の除去や歯髄保存方法など臨床の講義や、レジンの接着メカニズムの基礎内容など学ぶことができました。
今回の講義を受けて、多数歯へのラバーダム防湿の方法を知ることができたため、セミナーが終了した翌日に、院のスタッフに協力してもらい、実際の口腔内に多数歯へのラバーダム防湿を行ってみると、歯牙模型で行うよりも素早くラバーダム防湿をすることが出来ました。講義でもありましたが、ラバーが歯牙をよく滑りました。しかし、歯牙模型どうよう前歯の歯頚部にラバーが入れることが難しかったことと、装着に時間がかかりました。
今まで根管治療をするときにしかラバーダム防湿をしたことがなかったですが、実際の患者で小臼歯へのCR充填を行う時にラバーダム防湿をしてみましたが、ラバーダム防湿をすることに10分ほど時間を掛けてしまいました。術前準備にかかる時間が増えてしまいましたが、充填処置は今までよりやりやすかったです。
辺見先生の話でありましたが、ラバーダム防湿は、「治療に責任を持つこと」につながると感じるため、ラバーダムを装着いて行える症例には、可能な限り行いたいと思います。
今後、多数歯へのラバーダム防湿を常習化するには、術前準備の効率化と前歯部への対応をなれることが必要だと思います。現在の自分のアポイント状態を考えると、まずは、操作に慣れることを目標に最低でも1日1症例以上行うようにしたいです。
辺見先生の講義で、症例発表はよくやった方がいいと話がありました。今回のセミナーで症例発表の準備をして、自分の治療の見直しと1つ1つの行動に理由を考えることができました。先輩からフィードバックをもらうことができる機会も勉強になるため、セミナーが終わっても続けられるようにします。
1期第4回
○感想文
前回の辺見先生による歯髄の診断やう蝕除去、歯髄保存の講義の知識があった分、今回の歯内療法学の内容が非常にスムーズに理解することができました。真っ当な歯内治療を行うためのエッセンスを治療難易度から診査診断、術式に分けて構成されていて、とても知識の整理に役立ちました。特に、歯内療法の分野は肉眼ではなかなか状況を確認することができず、正しい知識と根拠を持って介入しないと成功しない領域であるため、曖昧な状態で介入してしまっていた自分に深く反省しました。
講義内で、エンド治療でやってはいけないこと③盲目的な治療(治療コンセプトに対して・術野に対して)というスライドがありました。前回、辺見先生も、なんとなくでう蝕を削る治療はやめてほしいと述べられていましたが、その通りで、きちんとした診断と、それに応じた術式がなければ真っ当な歯科治療はできません。我々若手の歯科医師が身につけるのは闇雲に手を動かすのではなく、一症例ずつきちんと分析し、正しい時期に正しい介入をしてそれを振り返ることです。現在、自分が初診から担当している患者さんの治療が少しずつ増えてきましたが、曖昧な知識やコンセプトで挑んだ治療は失敗に直結します。自分が治療をしたせいでその歯の状態が悪くなることは絶対にあってはいけないので、若手の内から真っ当な歯科治療を行うことを徹底し、それが可能な診療所に身を置くべきだと痛感しました。
術式に関しては、これまで弯曲根管の根管形成や、緊密な根管充填に対して苦手意識を持っておりましたが、それ以上にアクセスキャビティやストレートラインアクセスといったプロセスにより時間をかけるべきで、正しいアクセスができていなければ後に続く根管形成、洗浄、充填にも悪影響を及ぼすことを学びました。現状では、エンドに非常に時間がかかってしまい、治療の進行が遅いですが、ステップを飛ばすと失敗に繋がるため、時間をかけても丁寧に治療することを忘れてはなりません。
第二回目の加藤先生によるペリオから、修復、エンドと、日常的に行われる治療のエッセンスをこれまでたくさん学ばせていただきました。どの分野においても言えることは、やはり真っ当な歯科治療を行うためには、適切な診療時間と正しい知識で予防的処置を全うする必要があります。保険診療の流れで考えるのではなく、患者利益を常に考えて、腕を磨いていきたいと強く感じました。
今回の田中先生の講義の中で“真っ当な歯内治療”を行うことが今後の歯科医師人生の中で一つ大きな土台になると感じました。何事にも基本に忠実に行うことが大切であり、歯内治療は日本の制度上、評価されず良質な治療を行えない部分があることを知りました。
予防の中でも歯内治療が必要になることは普段の臨床の中でもまだ多くあります。治療のサイクルの中で一回の治療を少しでも長く長期的な予後が望めるようにすることが大事であり、歯内治療はサイクルの中でも後の方に来るものであることからとても重要な分野であると思います。そして、良質な治療と予防メンテナンスの環境の基盤があって初めて治療の価値が出るとういうことを学びました。
歯内治療は普段の臨床においても悩むところが多くありましたが、田中先生の講義を聞いて複雑なイメージを単純化することができました。
歯内治療を行う上で単純なケースが少ないということを頭に入れて考察することが大切と思いました。その上で、治療が適切に行えるかどうか、難易度の評価を事前に行う必要があることを学びました。事前に把握しておくことで、必要最低限のトラブルは回避できるものと考えます。そもそもこの症例は自分で治療を行えるかどうかを判断の見極めが重要だと思います。
無理な治療を始めてしまうことは、術者、患者双方にメリットはなく、自身が対応できるかどうか判断するために、今後多くの症例を見ることになる中でも、欠かさず事前の評価を行うことが重要だと感じました。そして、根管治療のステップアップを大切にしていきたいと思いました。
診査診断の点でX線写真を撮る際、より多くの情報を得るために偏心投影を行うなど、まずは最小限かつ多くの情報を得るようにすること。より正確で多くの情報が得ることのできるC Tもむやみやたらに撮るのではなく、必ず利点、欠点やA R A R Aの法則を意識しておかなければならないと感じました。
歯内治療が複雑だというイメージを今回は各ステップごとに見ていくことで解消できました。大事なことは基本に忠実に行うことだと感じました。中でも治療において最小限の切削などのM Iの概念は大切ですが、それを意識しすぎてかえって複雑化することがありました。後の治療のステップを確実に行うために必要な切削も考えながら治療を行うことように意識すること、切削のメリットを考えながら治療することが重要だと感じました。
真っ当な治療を行うために、適切な診療時間の確保、拡大視野、治療効率を高めるマテリアルの使用を3つポイントを治療経験の浅い時から怠らず取り組んでいきたいと思います。
まずは、基本に忠実に治療を行うこと、エビデンスに基づいた原理原則を常に意識して行うことが何より大切だと感じ、日々の臨床に取り組んでいきたいと思います。
私は今回の講義を受けて、3つのことを学ぶことができた。
1つ目は、エンド治療を行う上で行ってはいけないことである。田中先生より、完全歩合制の給与形態、保険算定から逆算した診療時間の配分、盲目的な治療の三つを教えていただいた。日本の保険制度では、包括化により真っ当な治療を行うための処置(ラバーダム・う蝕象牙質の除去・隔壁・マイクロスコープ・頻回な根管洗浄など)が評価されていない。1回の根管治療での算定点数は平均500点で、歩合制であれば1000円の収入と想定される。自分が経営者になった場合、かなり厳しいことになると理解できた。真っ当なエンドを行うためには、適切な診療時間と拡大視野と効率を高めるマテリアルが必要であると学んだ。現在保険外診療としてエンドをさせてもらえているため、その中で真っ当な治療を実践していきたい。
2つ目は、解剖学的形態である。根管は、シンプルな円形の管ではなく、扁平な部分があったり、根尖で湾曲していたり、根管同士が複雑に繋がっていたりする。また、解剖学的形態の複雑さから、上顎2番、下顎1・2番、下顎6番は既根管治療歯のうち、根尖のエックス線透過像の発生率が高い1)と学んだ。振り返ると、上顎2番は根尖病変がかなり大きく、境界明瞭で嚢胞化が疑われる症例をかなり経験したが、斜切痕や根尖分岐、扁平部の偏位など、エンドが難しい理由があることをやっと理解することができた。
3つ目は、適切な症例選択についてである。アメリカのGPが自分で行う再エンドは、1割のみであり、残りは専門医に依頼している。理由としては、他のGPが真っ当に行って上手くいかないのであれば、それだけの難しさがあり、自分で上手くいく保証がないからだそうだ。日本の場合、真っ当な治療が行われていない可能性という点で、トライする価値はあるかもしれないが、レッジやアピカルトランスポーテーションなど再治療の難易度が高くなっている確率が高く、また再治療によるパーフォレーション・マイクロクラックを与える可能性など長期予後を脅かすリスクも伴う。また、エンド由来でない疾患(アロディニア・ハイパーアルゲジアなど)との鑑別診断も重要である。今回の講義の内容と、米国歯内療法学会の根管治療症例における評価用紙を用いて症例の難易度を把握し、自分で行うか専門医に依頼するか適切に判断していく。まずは単根管のイニシャルなケースから経験していく。
最後に、エンドの分野は、材料の進歩が著しい中、コンセプトは昔から大きくは変わらないため、エビデンスや各学会のガイドラインが充実していると改めて感じた。盲目的なイメージで治療するのではなく、エビデンスやコンセプトを明確な上で真っ当な治療を実践していきたい。
今回は歯内治療をメインで田中先生に講義をしていただきましたが、正直なところ歯内治療は苦手意識があります。というのも、根の形態が複雑でそもそも治療自体が難しいのに、治療後疲弊した状態でレセプトを入力している時、その点数の低さに虚しさを感じてしまいます…。もちろん報酬のために治療をしているわけではないですが、現実を見ると少し悲しい気持ちになってしまう自分もいます。
そんな中で田中先生には”真っ当な治療”というテーマでお話をしていただきました。専門医の先生ですら1時間以上かけて治療を行なっているのに、私の友人の歯科医院では”30分で診療を回すように”と言われているということですが、それでは真っ当な治療など行うことができるはずはありません。幸い私が勤務している歯科医院ではゆっくり診療時間を確保してラバーダムを行って治療することが当たり前になっていますが、多くの方がそのような環境下ではない状態で根管治療を行なわれているという歯科医療の現状にも、改めて考えさせれられるものがありました。また、根の解剖学的形態の把握などは二次元的なレントゲン画像ではつい見落としがちになってしまうので、今自分が見ているものが真実を写しているとは限らないという視点を持つ必要性も感じました。
歯内治療を行うにあたって、診断はとても迷う部分です。前回の辺見先生のご講義とも少し重なりますが、深在性う蝕の治療方針には頭を悩ませることが多くあります。ただ、今までの自分を省みると、やはり診断に甘さがあったようにも思えました。レントゲンの読影や診査など、術前に十分精査をしていなかったために結局後手に回ってしまった部分は多くあります。例えば、インレー辺縁部の歯質の破折を主訴に来院されたメインテナンス中の患者さんに対して、レントゲンで歯牙及び根尖部に異常所見がなかったため、FMCをそのままセットした患者さんが、数ヶ月後のメインテナンスで辺縁歯肉に瘻孔をつくってきてしまった、という症例です。歯髄の診断を怠って最終修復をしてしまったために、無駄なステップを踏んでしまいました。根管治療を開始したものの、根管が見つからず、瘻孔も症状も消失しませんでしたが、CTを撮影して根の形態や見落とした根管がないか確認したり、マイクロスコープを用いた拡大視野下での治療を行なったりしたところ、根管全てを洗浄できる状態になりました。結果として、無事瘻孔や症状は消失しました。それまでに時間や労力がかかりましたが、田中先生のおっしゃる”真っ当な治療”を実現すれば、結果はしっかりついてくるのだと実感した瞬間でした。何より、患者さんがその歯を気にせずに食事をすることができるようになったと教えてくれたことが本当に嬉しく感じました。ただ、これで終了ではなく、引き続きメインテナンスでレントゲン写真を撮影して経過は追っていきたいと思っていますし、同じようなことが2度と起こらないよう、どの患者さんでも歯髄と根尖部の診断を確実に行なった上で治療にあたるよう気をつけるようにしています。
もちろん、この失敗からの学びで完全ではなく、診断の目もたくさんの症例を重ねてもっと養う必要はありますし、技術面もストレートラインアクセスがあまりできていなくて根管充填がうまくいかないこともあります。そこはこれからの課題としながら、何かつまづいた時には絶対にどこか見落としがないか先生のお話を思い出しながら日々の診療にあたっていきたいと思いました。また、苦手意識はあるものの、MTMを行った上で必要になった治療はきちんとしたものでなければ、結局ドリル&フィルの悪循環から脱却することはできないので、練習を重ねて患者さんに”真っ当な治療”を行うことができるよう、日々精進していきたいと感じました。
今回も貴重な経験と多くの学びを与えていただき、ありがとうございました。
田中先生の講義で印象的だったのは「真っ当な歯内治療を目指す」という言葉です。先生が最初に受講生に聞いてくださった「ベストなパフォーマンスを出す条件」。私たちが思いつく、正しいと思うことをする、それが歯内治療の根本なのだと思いました。また、保険点数だけみると、非現実的な点数設定がされていることも知り、悲しくなりました。目先の利益のみを求めるのでなく、医療の心をもって誠実に治療を行える、今の環境に大変感謝します。
ストレートラインアクセスの重要性は講義を通じて痛感しました。専門医の田中先生も、かなりの時間をアクセスキャビティにかけているのとことでした。天蓋残存によって、根管洗浄や側方加圧が不十分な症例も共有していただき、ストレートラインアクセスがあることによる臨床成績の差を感じました。自分の臨床を振り返ると、根管へのアクセスを焦って、あまりストレートラインアクセスを意識していなかったです。加えて、感覚的に歯質を残存させたい思いがあり、十分なサイズのアクセスキャビティが形成できていなかったようにも思います。アクセスキャビティの大きさと細菌除去の関係も知り、歯内治療成功のために十分なアクセスキャビティが必要だと認識しました。自分は臨床経験が浅く、根管形態の理解も乏しいため、ニンジャアクセス等を意識するのではなく、基本に忠実な診療を行いたいと思います。今後歯内治療の際は、アクセルキャビティの形態が分かる写真を必ず撮影し、振り返りできる資料を残そうと思います。一歩一歩改善、成長していきます。
ファイルの号数の違いからくる断面積の増加率は講義で初めて意識しました。10号、15号のルースファイルは極めて重要で、根管形成は急いではいけないと学びました。ついつい焦ってしまう根管形成ですが、一つ一つの手技の意味や重要性を知ることで、丁寧な診療が行えるように思います。
講義を通じて正しい手技やエビデンスを知ることができて大変うれしく思います。歯内治療はなかなか見えにくい治療であるため、自分の診療がこれでいいのか不安に思うことが多々ありました。今後は講義の内容を踏まえて、一つ一つ、診療の質を向上していこうと思います。
私は根管治療の経験がかなり浅くかつ田中先生の専門的な治療を側で拝見させて頂いているからこそ、根管治療というのはかなり難しいものという意識が強かったのですが今回の先生の講義をお聞きして、基本に忠実に時間をとって取り組めば大きな失敗はせずにできるのではないかと思うことができました。やはり根管治療というのは、もちろんルーペやマイクロスコープ等の拡大鏡を使用すればある程度の部分まで視野に入れることが可能ではありますが、盲目的になる部分も多いからこそ誤魔化して治療をすると失敗をしたり、後で症状が出たときのリカバリーが大変になると改めて感じました。
先生から最初にご提示のあった、専門医の治療に必要な要素は何かという点に関しても、もちろん技術的な部分や器具や費用の面では足りない部分が多々あるとは思いますが、正確な審査診断や可能な限りの環境整備、時間(これが1番大切だと思いました)等は私自身の努力や勤務先へのお願いにより整えることが可能であると思いました。先生もお話されていたように、単根管歯でも歯牙の形態やイスムスの存在など解剖学的形態が複雑になることもあるため、まずは治療する歯牙の根形態がすぐにイメージできるようにアトラスなど資料をよく見て覚えるところから始めたいと思います。また環境整備に関しては、私はありがたいことに田中先生がいらっしゃる医院に勤務させて頂いているため器具が何でも揃っている所で治療を行うことができます。しかしいい器具が揃っていてもそれを迷うことなく上手く使いこなせれば意味がないため、同じ目的のための器具でも自分が使いやすい種類を練習を重ねながら見極めて治療の時にスムーズに使えるようになりたいと思います。
また時間に関しては、先生も重々お話されていたように時間に圧迫される中では最適な治療は絶対にできないと思います。私も焦ってしまうと、必要な審査や画像撮影を飛ばしてしまったりやり方が塑造になってしまうことがあるため、慣れてくるまでは時間を取らせて頂きその分一回一回の治療に全力で取り組んで、確実にステップアップできるように努力したいと思います。
エンド症例の治療にも今まで学んできた患歯の審査方法や診断の付け方、治療にあたってラバーダムをかける等活かせることが多々あるため、復習も兼ねてこれまでの知識を活かせればいいなと思います。
田中先生の歯内療法学の講義では、「エンド治療で大切なこと」から始まり、根管治療の難易度について、診断・治療方法の講義を受けることができました。私は、学生の頃からの歯内療法の講義が苦手であり診療でも、特に自信を持つことのできない治療でしたが、田中先生の講義はわかりやすく、今まで理解したつもりになっていた内容のも、知識の整理ができたと感じました。
今回の講義を受けて、根管治療の難易度についての内容であった、「下顎前歯部の根尖透過像の残存率」は実際の臨床を通じて感じることがあり、とても納得しました。私が始めて行った臨床現場での根管治療の部位は、下顎の中切歯であり、根尖透過像が残存してしまい、苦い思いをしました。今になって、根管形態を十分に把握していなかったと思いましたが、その時は、治療技術の未熟さを悔しがり、改めて歯内療法の教科書を読みなおしましたが、今にして思えば、治療中の写真を撮影し先輩ドクターにフィードバックをもらうようにすればよかったと思います。
講義を受けることで多くのことを学べますが、このセミナーに参加したことで、学んだ知識が実際の臨床に落とし込めているか知るためには、症例発表を行うことが大切さであると感じています。
今回の講義を受けて、根管治療方法を再度学ぶことができ、基本の大切さを感じました。田中先生の課題では、症例発表のフォーマットがあり、どのように症例をまとめたら良いのかを知ることができました。今後は、このような形式で症例をまとめて先輩ドクターからフィードバックをもらえるようにしたいと思います。
田中先生をはじめ、熊谷先生、石山先生、家泉先生、この度は参加できない状況にもかかわらず、ご配慮いただき、田中先生の講義を拝聴することができ、大変うれしく思います。本当にありがとうございます。歯内療法は初期治療の中でも特に目で見えない領域の治療であり、自分が行った治療が正しかったのか、最善の治療が行えているのか、正しく評価することができているのかも、いろいろなことが不透明なまま今まで来ているように思います。田中先生の講義で何度もおっしゃっていた“真っ当な治療”をするのは簡単ではないと感じると同時に、一つ一つの工程をしっかりと踏めばすごく難しいことでもないということも分かりました。私は現在勤めている福田歯科医院のシステムのおかげで、根管治療に毎回2時間近く時間を確保できています。どんな治療もそうだと思いますが、根管治療は特に見えない分焦ってしまうことが多いような気がします。私は特にコロナルフレアリングからグライドパスまでの工程はとても焦りやすいです。心の余裕を持てる意味でも時間の確保は非常に大切だと思っています。たくさんの患者さんを診ることはできませんが、一つの症例と向き合える時間や環境が整っている分、“真っ当な治療”を確実にしていかなくてはならないと強く感じました。当院、残念ながらマイクロはないのですが、治療前に必ずCT撮影を行ってから取り組んでおります。やはり、CTがあることで3次元的な形態や根管の走行を把握してから介入できることは非常に大きなメリットを感じています。必要以上に歯質の切削を回避できることやパーフォレーションのリスクを下げられると思います。しかし、デンタルの撮影は根充後にしか行っていませんでした。今までの治療でも根充をしてからアンダーであることがわかり、再度根充をやり直す経験があります。患者さんにしっかり説明をした上で、ファイルやガッタパーチャ試適のデンタルを撮影し制度を挙げていきたいと思います。実際の治療工程では、特に穿通や作業長を測ることばかりに気持ちが優先してしまい、ストレートラインアクセスできていないこともよくあったと振り返ることができました。早く終わらせてあげたいと思う気持ちから、どんどん次の工程にいこうとしてしまいがちですが、一つ一つのステップを慎重に進んでいかなければ、より時間がかかったり失敗する原因になってしまったりするのだと改めて感じました。器具の到達の具合や、プレカーブの必要性、根管拡大の方向や根管洗浄の時間、あとはスプレッダーの挿入方向など、様々な細かい手技や考え方が、初めて知ることもあれば習ったのに忘れてしまっていることもあったので、非常に勉強になりました。根管充填の際に使用するメインポイントも規格性にばらつきがあることも忘れていました。アシストの方にメインポイントを出してもらっていますが、メインポイントの選択も自分自身で行うべきだと思いました。根管治療を進めていく際に、自分が行う手技や方法を、一つ一つ根拠を持って取り組まなければいけないなと感じましたし、それがその歯に責任を持つということにつながると思いました。そして、根管の複雑な形態や走行を知ったり、根管治療の難しさを感じたりすればするほど、根管治療に至らないよう予防することが1番大切だと、つくづく感じます。貴重なご講演本当にありがとうございました。次回の発表の際には、またよろしくお願い致します。
今まで、エンドの治療にはとても苦手意識があり、やりたくないなと思いながらいつも治療を行っていました。特に、急患の複根管の抜髄は、今でも正直、本当にやりたくないと思っています。
その原因になっていたのが、エンド治療でやってはいけない盲目な治療だと今回の講義を聞いていて、気づきました。
また、抜髄や感染根管治療に苦労しているのは、自分だけ。自分の技術不足で時間もかかるし、なかなか治らないと思っていました。
しかし、複根管の根治がいかに難しく、とても高い技術が必要とされることを改めて知りました。ほっとした気持ちと、もっと上手になりたいという気持ちになりました。
私は、幸せなことに、正しいことをしっかり行える、時間と回数を与えて頂けているため、真っ当な歯内治療を意識して今後も取り組んでいきたいと思いました。
また、歯の解剖学的形態や部位ごとに異なる難易度を理解し、敵を知ってから治療を行わなければいけない事を学びました。また、何も考えずに治療をする怖さを思い知りました。そのためには、正確なレントゲン写真、アクセスキャビティー、ストレートラインアクセス、根管拡大など、一つ一つに意味があり、どれか一つでも疎かにすると全てうまくいかなくなってしまうということを改めて学び、その重大さを日々の臨床でひしひしと感じているところです。
根管治療のステップアップとして、実臨床で症例を選んで小ステップから治療をしていくのは難しいけど、まず、単根管の抜髄を完璧にマスターできるように努力していきたいと思いました。うまくいかないこと、失敗などたくさんの壁に当たってきましたが、これからも学び続け、苦手意識を少しでも克服できるよう、小ステップをクリアしていきたいと思いました。
また、今回、アクセスキャビティー、根管形成、根管形成、根管貼薬、根管充填など、詳しく教えてもらえて本当によかったです。今まで、正直なところ、”教科書に書いてあったらから”、”上の先生がこのやり方をしているから”となんとなく真似をしてやってみたりしていた部分がありました。しかし、今回の講義で、正しい方法や、なぜそうした方が良いのかとか、新しい学びと、再確認をすることができました。また、知らなかったことや、注意することなどもう一度復習をし、今後の臨床ですぐにでも挑戦していきたいと思いました。
歯内治療について、モヤモヤの真っ暗な霧の中で治療をしていたけど、今回の講義を聞いて、少し希望が見えてきたと同時にもう少し頑張りたいという気持ちになることができました。ありがとうございました。
田中先生の講義を受講し、歯内治療に対する考え方が大きく変わりました。専門医による治療というのは、GPの先生方が行う治療とは大きくかけ離れているもの、届かないものだ
と思っていました。治療技術に関してはもちろんの事ですが、適切な治療をどれだけ丁寧に、当たり前に、継続して行えるかという点が大きく異なることではないかと感じました。それを行うためには、短い処置時間、ましてや保険点数を考慮したような治療では患者さんを幸せにする事が出来ません。技術に関してはかなり長い時間をかけて身に着けるスキルになりますが、診療時間の確保に関しては自分の努力次第で作ることができます。実際の診療でも、症例によっては1回あたり一時間、回数は問わず治療を行える環境にあります。しっかりと時間をとれる環境にあるのであとはどれだけ丁寧に適切な治療を行うことが出来るかが自分自身の今の課題だと思います。また、現段階では自分の技量にあった症例を選び適切に行っていくのも大事な治療スキルのひとつではないかと思いました。米国歯内療法学会では、根管治療の難易度を患者さん、診査・治療、その他考慮すべき点の3つで低い~高度の3段階評価を行っています。GPとして、難しい症例は専門医の先生に送るといった連携をきちんと行っていくことの重要性についても学ばせていただきました。
また、たくさんの症例を診させていただく中で、術野がすごく綺麗だと思いました。無菌状態で根管治療を行うためにも適切にう蝕除去を行い、ラバーダムをつけられるような隔壁作りが必須になります。そして以降の根管治療をスムーズに行えるようなアクセス形成が重要です。天蓋が残っているような状況下では後のファイル操作も難しくなってきます。
ストレートラインアクセスが根管治療を行う上で最も重要なステップという言葉が示すように、的確な根管治療を行うためにも特に時間をかけ意識して行いたいと思いました。今まで治療をしてきた中で、ファイルがまっすぐ入らず拡大に苦労した症例や、天蓋が残った状態で治療を進めてしまった症例があります。適切な治療を出来るように、綺麗な術野を目標の一つにしていこうと思います。
そして治療介入の大前提となる診査にも注力したいと思いました。根尖の状態や歯髄の状態は、歯周病のように数字として表すことが難しいため患者さんからの情報が鍵を握ります。当たり前ですが、患歯の状態の痛みの有無、症状、経過がどうなのか、痛みの程度や性状も含めて細かく確認することが的確な診断、治療に結びつくのではないかと改めて思いました。
歯内療法は目で直接見えないため苦手意識をもった治療分野の一つでした。しかし講義を受け、見えない治療であるからこそ、診査、診断を適切に行い、自分の技量に応じて症例を選び専門医の先生と協力するといったとても奥の不快分野であると感じました。今自分自身の与えられている環境も含め、じっくり治療に向き合えるのか、そして単根の症例から治せる治療を行っていきたいと思いました。
1期第5回
○感想文
熊谷先生のお話を今回の講義で再度直接お聞きすることができ、先生の熱意を生で感じ取ることで再度MTM治療にしっかり取り組まなければならないと思うことができました。
MTMの治療の意義、流れなどは現在勤めている川勝歯科でも学んでいますが、熊谷先生のお話をお聞きしMTM治療の根本にある歯科治療の問題、そこに対して先生が提唱されている想いをより一層学ぶことができました。海外と比較して日本人のハイクラスの人達の口腔内への意識の低さを先生が強調されて仰っており、そこには予防歯科の浸透度の低さがあることを実感することで、これは私達予防歯科に積極的に取り組もうとしている歯科医師が業界をさらに変えていく必要があると思いました。また国民皆保険制度によって日本人は誰でも治療が受けられるという意識が問題であるという観点について、私は意識したことが少なかったため保険診療についても今後は意義から考えていく必要があると思いました。
先生の授業を通して、今後私達は熊谷先生が道筋を作って下さった方向に乗りながら日本の歯科診療の根本をさらに変えていく担い手になる必要があると感じました。それは簡単な道のりではないですが今回参加した若い先生方と協力して変化を起こしたいと強く思うことができるいい機会となりました。
私は他の先生方と違った働き方(予防型歯科の医院と総合病院の歯科勤務)をしているため、常時MTM型の治療に向き合っている先生方よりも知識や技術面で劣るところがあり、今回のセミナーにもついていけるか不安がありました。しかし、講義や実技を通して先生方から学ぶことが多々あり、生涯を通して自身の歯を残すことの重要性を再度実感しました。口腔内の問題に苦しんでいる有病者や高齢の方を常にみている立場だからこそ、今後の日本を担う若い人にKEEP28の重要性を伝えていく任務があると強く思うことができました。今後は総合病院での経験例も含めた自分の考えや症例を提示し、2つの全く異なる観点からみている環境を強みにできるように努めていきたいと思います。
約半年間のセミナー、最後の熊谷先生の講義を聞いて抱いた正直な印象として、振り出しに戻ったというものでした。
12月に酒田に来て、熊谷先生のはじめの講義、予防をもとにした日本の歯科医療の改革への活動とM TMとはなんなのか、何をもたらすことができるのかということから始まりました。もともと、M T Mを中心とした診療に携わっていましたが自身の認識の甘さを感じることになりました。M T Mは一つの診療体系、システムのようなものという認識が大きく間違っていたことに気づくことができました。
今回のセミナーでは、予防を行う上では治療の質も高度なものでなければいけないことから、各治療の専門医の先生方の講義を受け、臨床の質の向上につなげることができました。そして、今回学んだことで質、技術の向上を実感することもありましたが、何より自分の中での自信につなげることができたという変化を感じました。治療に対する自信ではなく患者さんに向き合う自信です。M T Mをまず自身で見ていく中で、患者さんへのアプローチの熱量が変わったと感じました。
適切な治療を行うための関係の構築に努め、妥協なくお互いベストを尽くすことができるように、常に真の患者利益を目指す姿勢を持つこと。患者さんの行動変容を促すのは初期治療の部分だけでなく治療を含め、メインテナンスまで全ての流れにおいて必要な要素であると考えます。それぞれに関わる、歯科医師、歯科衛生士、スタッフで医院として同じ方向を向いて取り組むものだと感じました。
患者さんの健康価値観の向上では、まずお互いの理想の共有をして一緒にゴールを目指すことが重要であると感じ、M T Mはそれを実現できるものだと思います。ただ、言葉では言えるけれど、実際に行うには易しいものではないことを熊谷先生のこれまでと、これからの取り組みを講義で聞き、強く感じました。
どうすれば日本の歯科医療を変えることができるかということに対して、保険制度、大学教育、行政、歯科医院、国民の意識改革、メデイアの適切な情報提供など大きな壁が多々あるということ。一歯科医院単位においても診療室内、外やDr、スタッフの教育、患者の価値観教育、地域への活動など多くの壁があることを学びました。今後、予防に携わり明るい未来を目指す上で、責任と覚悟を持たなければ達成できないと感じました。
国、国民を変えるには、歯科においての予防が国民の健康の向上につながることができるということを実際に示すことができなければ、新しい価値を作ることができません。長期にわたるデータを蓄積し、実証できるということに今後私たちは取り組んでいかなければならないと感じました。
熊谷先生の取り組みから数多くの予防に携わる歯科医師によって達成できると信じて、今回のセミナーを踏まえて、振り出しに戻りこれから努めていきたいと思います。
1日目は体調不良で現地への到着が遅れてしまい、最後の30分しか講義をお聞きすることができなかったので、少しだけお聞きしたお話の感想をまとめさせていただきます。
熊谷先生は技術面でも大変素晴らしいと聞いておりますが、そこでひとりよがりになるのではなく、周りを巻き込んで突き進んでゆく姿勢に対して本当に尊敬の気持ちでいっぱいになりました。というのも、学校検診で口腔内写真を撮影し、記録していったと共に、保護者や(小児を教育するための)先生方を指導することは自分ひとりだけで取り組むことはできません。自分の医院のスタッフに歯科医療従事者としてのミッションを共有し、同じ目標に進んでいくよう指導できるということがまず素晴らしいと感じました。
日々の臨床をされている中で、こういったセミナーを開催するだけでなく、海外の歯科医療を取り巻く環境にもアンテナを張っていらっしゃる姿も印象的でした。周術期のお話は私も以前耳にしたことがあって衝撃的でしたが、それが本来あるべき歯科医療の姿であることを再確認しました。と同時に、大学時代、周術期の診療科を見学した時、「なんでこんな抜歯しなければならない歯が口腔内に残っているんだろう」「どうしてこんなにセルフケアができていないんだろう」といった疑問がポツポツと自分の中に湧いていましたが、臨床に出ていない時の自分が感じた違和感は、案外そのまま日本の歯科医療の改善点であると、ふと思いました。ただ、その違和感を改善しようと実行に移すことが難しくて、それをやり遂げる熊谷先生は、歯科医師としてだけでなく、人として尊敬すると感じました。
このOPセミナーがスタートしたと同時に私も初期治療から患者さんの診療をスタートしましたが、だんだん初期治療を重ねるうちに患者さんへの愛着が湧いてしまい、抜歯したくない、被せたくないといった要望を受け入れたくなりました。しかし、先生のご講義の中で再評価②がとにかく大切で、ホームケアがしやすい口腔内にした状態でメインテナンスへ移行しなければならない、というお話を聞いて、ふと我にかえりました。予後不良の歯を残すということは、患者さんがセルフケアをどんなに頑張ってもその見返りを受けることができません。患者さんの要望を聞いてそれを叶えるだけでは本当の患者さんへの利益にはならないと思いました。
また、メインテナンスのスタートが早ければ早いほど喪失歯は少なく、症例によっては家族にも来院してもらった方が良いという場合もあるというお話を再度していただきました。自分の担当患者さんのご家族やご友人を連れてきてもらいたいと思って必死にやっていますが、自分の担当している十数名の中で紹介してくれた、という方はまだ一人もいらっしゃいません。中にはお子さんがいらっしゃるという方もいますが、なかなか一緒に通っていただくことができていないのは、私がその重要性を伝えきれていないからではないかと感じています。と同時に、これからもその重要性は話していくつもりですし、このセミナーが終わってからこそ本当の始まりだと思って、また頑張っていこうと気持ちを新たにしました。もちろん私の課題はそれだけではありませんが、熊谷先生のご講義からは考えさせられることが多く、今のままではいけないという気持ちを奮い立たせてくれます。感想をまとめながら出てくるこの気持ちをこれからも忘れないようにしていきたいと思っています。
貴重な機会をいただき、ありがとうございました。
熊谷先生の最終講義を受け、改めて先生の熱い想いを肌で感じるとともに次世代を担う私たちがこの歯科界を良くしていかなければ患者さんを幸せにすることが出来ないと感じました。全5回に渡り、歯周、保存、歯内治療に関する基礎知識や手技的な部分もたくさん学ばせていただきましたが、一番歯科医師として難しいのが患者さんとの関わり、行動変容をいかに行うかという治療の土台部分であると思います。このセミナーが初まってから68人の純初心、再初診の患者さんを見ましたが、患者さんの心を動かすというのは、本当に難しく、毎日が勉強の日々でした。悪いところだけ治療をしてくれればいいと思っている患者さんも中にはいらっしゃり、5人が初回の資料どりを終えた状態で中断になってしまいました。このような結果は私の知識や技量、熱意が十分で無く、患者さんにいかに歯を残すことが大切か伝えきることができなかったからではないかと反省しています。そして何より、本来あるべき歯科治療を提供するためには、十分に患者さんと向き合う時間や環境の確保が不可欠であると改めて感じました。今回は既成の診療体制に不足しているものを補うような形で、診療を行なっていました。やはり保険診療の中では時間を気にしてしまう部分があり、こちらも伝えたいことを伝えきることが出来ませんでした。熊谷先生よりイノベーション、改革というお言葉をいただきましたが、価値ある診療の提供をするためには自費化というのも非常に大きな意味を持つと思いました。自分が将来行いたい医療の姿が、セミナーや見学を通じてかなり明確になってきました。熊谷先生がこれまで日本に対して言い続けてきた自費化というのは、海外同様治療の技術を担保する上では必要なことだと思います。開業が自分の中での将来の目標の一つではありますが、バイオフィルムに感染した脳から脱却し1からあるべき診療体制を作って行きたいと思いました。
また講義の中では、たくさんの症例写真を見させていただきました。開業当初から現在に至るまで、同じ規格性で撮られている何十年にも及ぶ症例を見たときは、すごく感動しました。真摯に患者さんと向き合っているからこそ、患者さんはついてきてくださりこのような長期に及ぶ症例を見る事が出来るのだと思いました。
最終講話の中で一番心に刺さった言葉が、日吉歯科と先生方の違いはMTMをやらされているかどうかという言葉でした。私自身、この言葉が当てはまったからこそ、一番心に残り突き刺さったのではないかと振り返っています。やりたいけど、やれないという心の葛藤があるのが正直な今の感想です。世界に冠たる国民皆保険かもしれませんが、患者さんも、医療従事者も苦しめている部分が少なからずあるのではないかと思います。このセミナーが終わってからも継続できるかというのが、1つの課題です。熊谷先生や講師の先生方の話を聞き、正直凄いと思ってしまいました。世界的に見て当たり前の治療を行なっているだけだで、これが本来のあるべき歯科の姿であるということを聞き、脳についたバイオフィルを除去し、今回学んだ先生方と共に当たり前だと言えるような日本の社会にしていきたいと思います。
第一回目の講義で、熊谷先生の医療哲学を教えていただきました。今回の講義では、その医療哲学に沿った、熊谷先生の半生を知ることができました。
熊谷先生はステークホルダーとの関わりが大切とおっしゃられていました。自分は最初、地方拠点としながら、日本全体に影響を与えるステークホルダーとつながりを作るのは、難しいと思っていました。ですが、日吉歯科には熊谷先生が蓄積してきた膨大なデータがあります。その裏付けと、熊谷先生の信念があるからこそ、ステークホルダーを含めた多くの人が、酒田の日吉歯科に注目するようになったと知りました。土地や環境は言い訳にならず、何をするか、どう発信するかで影響力は変化することを理解しました。
また、日本の学校歯科検診は、熊谷先生のお力によって大きく改善したことも知りました。東北大学での探針使用についてのディスカッションは、大変白熱したものだったのでしょう。熊谷先生の努力のおかげで、歯科検診での探針の使用はなくなり、多くの学生がう蝕から守られることとなりました。熊谷先生は「敵も多かったが、だんだん味方が増えてきた」とおっしゃられていました。エビデンスに則った正しいことを行っていれば、必ず味方が増えてくることを、熊谷先生の生き様を見て学びました。
自分の診療室をどうしたらいいか考えたときに、5つのポイントがあることを教わりました。1.歯科医師の再教育。2.スタッフ教育。3.どのような患者に来てほしいか、どのような患者に育てるか。4.地域への啓蒙活動。5.診療室への投資は可能か。
そして前提には、全ての患者にあたり前にMTMが実践できる診療所作りがあると学びました。セミナーを通じてMTMの価値と、これは全ての患者が受けうるべき本来当たり前の医療であることを、自分も体感しました。今後、日吉歯科のように真摯にMTMを実践する歯科医院が増えることを願います。
熊谷先生は間違いなく日本の歯科界に大きなイノベーションを与えてくれたゲームチェンジャーです。それは、正しい医療哲学をもって、きっちり臨床を積み重ねてきた結果だと感じました。今回セミナー全体を通じて、熊谷先生の医療哲学を存分に浴びることができました。保険のバイオフィルムに感染する前の今の時期に、熊谷先生のお話をこんなにも聞くことができて、本当に良かったと思っております。今後も、熊谷先生の講義で感じた熱い情熱を絶やさぬよう、真摯に歯科医療に向き合っていきたいと思います。
半年間、誠にありがとうございました。
私は今回の講義を受けて、3つのことを学ばせていただいた。
1つ目は、熊谷先生の50年間は闘いの連続であったということだ。28歳で全て自費診療のクリニックを開業し、最初は大変もだんだん患者さんの口コミが広がったこと。酒田に移って同じスタイルをしたら、歯科医師会や行政から咎められたこと。歯科にイノベーションが必要と感じ、バイオフィルムの除去を歯科医師の治療目標としたこと。そのための診療所作り、スタッフ育成に力を注いだこと。世界標準の歯科を勉強し、日本で結果を示し、世界の基準を作り出したこと。メディア出演を行い、パイオニアとして日本の予防歯科の認知度に貢献されたこと。厚労省との闘いの末、数々の変革を行ったこと。そのためには、自分に妥協しないこと、患者さんと本気で向き合うことが大切であると学んだ。そして、それを可能とするためには、生涯学び続けることが最も重要と学ぶことができた。
2つ目は、地域の人々の口腔内を変えるためには、診療室で待っていては間に合わないということだ。どんなに自分のクリニックの患者さんの口腔内を維持したとしても、純初診でいらっしゃる患者さんが既に崩壊していたり、他院で多くの処置を受けていたりすると、KEEP28の達成は永遠に困難である。市民を教育し、民間企業に働いかけ、行政と協力することで、市の口腔衛生レベルを向上させることを、同時に行う必要があると学んだ。特に、市民啓発だけでは限界があるため、理解を示していただける民間企業の社長を教育し、トップダウンで社員を教育していくことが、最も効果を得やすいかもしれないと感じた。さらに、教育の場として、小中高生だけでなく、学校の先生に知識を与え、先生自身が生徒に教える立場になるということも、とても有用と感じた。診療所作りの先を見据え、地域へどうアプローチしていくか考えて行動していきたい。
3つ目は、自分の信念を貫くと、一緒に闘う仲間が増えていくということだ。自分の信念を追い求めると、まず同業者からの圧力や凄まじい反対を受けると学んだ。もしかしたら、その反対する人は、過去自分も同じことをして失敗した故のアドバイスなのかもしれない。その一方で、信念を貫き続けていくと、歯科関係企業の社長、市内の民間企業の社長、酒田市長、山口絵里子さんなど、同じように自分の信念に従って行動し続けている仲間に必ず巡り会えると学んだ。今後課題にぶつかったり、周りから反対されたりすることも多々あると思うが、例え一時的に世界の全員が敵に見えたとしても、自分の信念を貫き続け、いつの日か出会える本当の仲間と巡り会えることを楽しみにしたい。今回のセミナーでは、その仲間となるメンバーとあらかじめ出会えたことが、本当に大きな財産となった。
最終回、熊谷先生に初回に引き続き、熱い思いを語っていただき、日本の歯科医療の現状、真の患者利益とは何か、そして、私たち若手歯科医師が感じるべきこと、今後すべきことをもう一度考え直す機会となりました。私は今まで学生時代に何度か熊谷先生のご講演を聞く機会がありましたが、熊谷先生が訴えている本当の意味は理解できていなかったように思います。実際に臨床に出て、いい加減な治療や、歯の事を何も知らずに口腔内が崩壊している状態など、目の前で救いたい患者さんと向き合う中でうまくいかないことや葛藤したこと様々な経験を通して、熊谷先生のおっしゃっている意味を少しずつ理解してきように思います。また、頭で理解するだけではなく、この新OPセミナーでの経験で身をもって理解することができたと思います。熊谷先生は、日本の未来についてもお話くださいました。今後、日本が迎える急速な人口減少、増え続ける保険医療費、日本で働く歯科医師たちが、この保険制度の中で点数を取ることだけに信念を燃やし、予防もせず、いい加減な治療を繰り返していては国を圧迫し続け、結局は自分たちを苦しめているだけということに患者さんたちにも早く気付いてほしいです。患者さんが得られるものは少なく、むしろ失うものの方が大きいかもしれません。この日本の歯科医療の現状を変えていかなければならないと改めて感じました。50年の臨床をなさってきた熊谷先生が今まで行ってきた功績と努力に、本当に感銘を受けました。熊谷先生がお話してくださった他分野の方々との活動や国や行政への働きかけ、そして院内での徹底したMTMとスタッフへの指導等、これだけ多くの活動に信念を貫き、長年続けられていることに大変感動致しました。日吉歯科で直接その話を聞けた私たちはその思いをしっかりと継承しなければならない、と感じました。それには、今後も規格性のある資料を取り続け、診査診断をし、一人一人の患者さんと向き合い続けることだと思います。そして、熊谷先生がおっしゃっていた、健全な人が健全であることに対価を支払うべき、という言葉を聞き、それこそ価値のある歯科治療だということを患者さんにこれからも伝えていきたいです。そのためには、口腔が崩壊してからでは遅く、小さな子たちから伝え続けなければなりません。それには、熊谷先生がおっしゃっていたように家族単位で受診してもらうことが重要で、家族間でのリスクを下げることにも繋がります。そして各分野の素晴らしい講師陣の先生方から、この少人数でかつ自分の症例に直接アドバイスをいただき、このような貴重なセミナーに参加することができ、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。専門医の先生方から教わった考え方や知識は、予防を行った上に成り立つものということを忘れてはいけません。真の患者利益は、ここからの私たち歯科医師の進む道の先にあると思います。このセミナーで得た学びを今日からの診療で活かし、実践し続けていく必要があります。まだまだ、目の前の診療と向き合うことに精一杯ではありますが、歯科医療の現状を変えていくためにも、今回のセミナーで得た学びを無駄にしないよう、努めていきたいと思います。
今回、開業前の若手歯科医のための新OPセミナーを受講した理由は、メディカルトリートメントモデルを通して、どのようにしたら患者に真の健康利益を提供できるか追求したい、と言うものでした。勤務先の医院でメディカルトリートメントモデルにのっとって診療を行なっておりますが、ついついMTMというレールにのせて作業的に行なっているだけで、真の患者利益から目線を外してしまうことがあります。このままでは患者にkeep28を提供できないと思い、今回のセミナーを受講させていただきました。
我々若手歯科医師は診療手技的側面で悩むことが多々あります。ついつい手技的なことにばかり思考が偏ってしまい、いわゆる治療技術のノウハウを習得するためのスタディグループや勉強会に所属し、対症療法のみを追求しがちであります。しかし、実は若手のうちに身につけるべきことはそのようなものではなく、keep28を達成するためのエッセンスを習得することこそが必須です。
これまで、メディカルトリートメントモデルの根拠となる論文や研究などの知識に触れず、勤務先でのやり方に従って診療をしていました。今回のセミナーで、メディカルトリートメントモデルの真髄を担う知識を得ることができたため、『なぜこのような診療を行うのか』を明確な根拠を持って患者さんと向き合うことができるようになりました。
今回の熊谷先生の講義にもあったように、患者の疾病リスクを多角的に捉え、リスク分類に応じて治療方針やメンテナンスも含むアプローチを変えていく必要があります。メディカルトリートメントモデルにおける資料採得は、まさにリスクアセスメントであり、ただ口腔内写真やレントゲンを上手に撮るだけではありません。患者のカリエスとペリオのリスクを徹底的に調べ、原因となるリスク因子を患者から除外していく、これこそが本当の治療であり、原因療法です。そのためには我々医療従事者がリスクアセスメントを正しく行うことができ、病因論について深い知識を有しておく必要があります。リスクアセスメントを行い、患者に正しく伝え、原因療法を行なって、結果をモニタリングする、というメディカルトリートメントモデルの一連の流れは、やはり少人数ではうまく行ったかどうかわかりません。講義でも取り上げられていましたが、症例を蓄積することが大事です。今回の新OPセミナーは終了してしまいますが、多くの患者さんと向き合い、情報をドキュメンテーションし、フィードバックすることは継続していき、より深く患者さんの人生を診ていけるようなoralphysicianになりたいです。今回は、セミナーを受講させていただき、ありがとうございました。
今回、熊谷先生の講義を聞いて、改めてオーラルフィジシャンとして仕事をしていく上での大事な視点をたくさん学ばせていただきました。
この半年間で、MTMを行っていく上での”核”の部分を学ぶことができ、本当に大切で貴重な半年間になったと思います。半年前の自分と比べ、全く違った自分になったと思いました。
患者さんを、教育することによって患者さんを育て、地域の啓蒙活動を行い地域住民を育て、国に対しても自ら変革を求め活動し、日本国民を育てようとしている熊谷先生の歯科医師としての歩みに本当に感動しました。
どんな逆境にも負けずに、決して怯まず、正しいことをし続ける熊谷先生の活力本当に尊敬します。
自分は、周りに流されやすく、正しいことでも自分の気持ちを抑え、立ち向かうことを諦めてしまいます。そんな自分が嫌いで変わりたと思う反面、立ち向かう勇気がありません。飼い慣らされたふにゃふにゃなキツネの例え、あー自分だなと心の中で思っていました。
私はよく、環境や誰かのせいにして現実から逃げてしまうことがあります。しかし、その選択は全て自分が選択したもので、環境や誰かの影響なんて1%だってないことを熊谷先生を通して学びました。
熊谷先生のように、自らの信念と志を持ち、どんな困難にも立ち向かっていけるような人間に、歯科医師としてだけではなく、一人の人間としてなっていけたらいいと思いました。
また、MTMを行うこと、正しい医療を行うことの大切さを学び、本気の予防治療・本気の歯科治療を携え、決して妥協せず、真っ当な歯科医師をこれから先何十年も続けて行きたいと思いました。そして、日本国民全員が、当たり前のようにMTMを受診でき、口腔内に困ることのない世界にしていけるといいと思いました。日本の歯科界はまだまだ遅れていて、カリエスや歯周病のような稀な疾患が溢れてしまっているため、そんな日本を食い止め、変革していくお手伝いができる歯科医師の一人になりたいと思いました。
今回のOPセミナー全体を通して、予防・治療のノウハウだけでなく、もっともっと大事なことを学ばせていただきました。歯科医師としての心の成長という部分でとても有意義な時間を過ごすことができました。また、同じ志をもつ仲間、先生に出会えたこと本当に感謝しています。今後この経験を生かし、熊谷先生の志を受け継いでいけるよう、また、新しい人に伝えていけるよう努力していきたいと思いました。貴重なご機会を本当にありがとうございました。
このセミナーについて
OP Seminar
セミナー参加者は12月の第1回目を受講した後、第2回3月までの期間中、当院の見学を申し込むことが可能です。1回につき2~3日程度、同時期に2名までとさせていただきます。詳細については第1回目セミナーにてご説明致します。
各治療分野の先生方のセミナーについては現在内容を調整中です。参加者の方には後日詳細を改めてお知らせ致します。
今回のセミナーでは講義を聞くだけではなく実習や相互のプレゼンを含むため、これを実現可能な人数設定とさせていただきました。
これまで数多くのセミナー・講演を行ってきた経験から、既に臨床経験が長く従来の歯科医療を続けてきた方が新たに本セミナーの目指す診療スタイルを取り入れることは極めて困難であると考えております。そのため歯科医師としてスタートを切ったばかりで従来の歯科医療に染まり切っていない若手歯科医師に限定させていただきました。
Oral Physicianとして必要最低限の治療をできるようになることを目的としています。ご登壇いただく講師陣の中には専門医の先生もいらっしゃいますが、専門医の治療・高度な治療・ドラマティックな治療を目指すものではありません。基本的な治療を基本に忠実に実践するための技術を習得する内容になります。
実際の臨床に活かせる能力を身に付けるためには講義や実習だけでは不十分であると考えました。日々の診療の中で本セミナーの内容がどのように反映されているのかを互いに評価・考察し合うことで、参加者の皆さんがより早くそして確実に成長できるよう発表の場を設けることと致しました。
酒田市の積雪状況により来院が困難となる可能性があるため冬季のセミナー開催は行わないこととしました。また、第1回目受講後からMTMの症例を集めるのに十分な期間が必要であると判断致しました。
全5回にわたるセミナーすべてに参加して初めて完結する内容となっているため、日程的な問題によるいずれかの不参加も認めないことと致しました。また各講義・実習内容に即したケースプレゼンも必要となるため、環境面や勤務先の承認などでこの実現ができない場合は今回の受講はお断り致します。
同様のセミナーをもう1ターム実施する予定ですので、そちらをご検討下さい。
会場
日吉歯科診療所(酒田)研修室および診療ユニット
日程
○第1期【終了】
- 第1回
2021/12/04(土)〜12/05(日) - 第2回
2022/03/12(土)〜03/13(日) - 第3回
2022/04/16(土)〜04/17(日) - 第4回
2022/05/21(土)〜05/22(日) - 第5回
2022/06/18(土)〜06/19(日)
○第2期【中止】
- 第1回
2022/07/16(土)〜07/18(月祝)
※3日間 - 第2回
2022/09/03(土)〜09/04(日) - 第3回
2022/10/15(土)〜10/16(日) - 第4回
2022/11/12(土)〜11/13(日) - 第5回
2022/12/10(土)〜12/11(日)
開催内容
【第1回】
○2期(3日間)
1日め
14:00
開始
熊谷先生講義
MTMについて(石山)
17:30
諸連絡
懇親会場へ移動
18:00
懇親会開始
20:00
懇親会終了
2日め
8:30
受付開始
9:00
エビデンスに基づいた臨床について
(松本先生)
初診時ビデオ鑑賞
院内見学
規格性のある資料採得について
(石山・家泉)
12:00
昼食
13:00
実習
・資料採得
・初期治療
・メインテナンスプログラム
18:00
・終了
3日め
8:30
受付開始
9:00
MTMのおさらい(家泉)
ディスカッション
12:00
昼食
13:00
熊谷先生講義・総括
16:30
終了
○1期(2日間)
1日め
13:30
・受付開始
14:00
・諸連絡
・熊谷崇先生講義
・休憩
・MTMについて スライド+ビデオ
(石山・家泉)
・質疑応答
・写真撮影
18:00
・懇親会場へ移動
19:00
・懇親会開始
21:00
・懇親会終了
2日め
石山・家泉による講義・実習
8:30
・受付開始
9:00
・初診時資料採得について
12:30
・昼食
13:30
・初期治療について
15:00
・熊谷崇先生総括
・質疑応答
16:30
・終了
【第2回】
1日め
14:15
・MTMケースプレゼンテーション前半(一人15分)
16:15
・休憩(15分)
16:30
・MTMケースプレゼンテーション後半
18:30
・休憩(10分)
18:40
・熊谷崇先生総括
19:00
・終了
2日め
北欧歯科 加藤雄大先生
(EFP(ヨーロッパ歯周病学会)クリニカルガイドラインから学ぶ、世界標準の歯周治療)
9:00~10:30
・なぜMTMの初期治療として歯周基本治療が必須であるか?(歯周病の病因論、歯周治療の特性)
・歯周病の新分類
・歯周病に罹患した歯の予後判定、治療計画
10:30~12:00
・歯周治療ステップ1(口腔衛生指導、リスク因子のコントロール)
・歯周治療ステップ2(原因除去療法、SRPの手技)
13:00~14:30
・歯周治療ステップ2 続き(非外科治療の可能性、歯周治療のゴール)
14:30~16:30
・歯周治療ステップ3(基本的な歯周外科治療:アクセスフラップ)
・歯周治療ステップ4 メインテナンス
16:30
・終了
【第3回】
1日め
14:15
・歯周治療ケースプレゼンテーション前半(一人15分)
16:15
・休憩(15分)
16:30
・歯周治療ケースプレゼンテーション後半
18:30
・休憩(10分)
18:40
・熊谷崇先生総括
19:00
・終了
2日め
恵比寿ヘンミデンタルオフィス
辺見浩一先生
・保存修復治療における診断の重要性
・臨床の中で生活歯髄とどのように向き合っていくか
・ドリリング&フィリングからの脱却
・MIを臨床の中で本当の意味で実践するために必要なこと
・齲蝕除去の最新の考え方
・修復と歯髄、歯髄保存治療の長期経過を担うのが接着修復
・介入が必要な「深在性齲蝕」とは?
・拡大視野の必要性
・修復処置のケースセレクション
・ダイレクトボンディング
ーダイレクトボンディングとは?
ーダイレクトの窩洞形成
ー接着の基本的な知識
ー歯牙の解剖学的形態
・インダイレクト
ーセラミック修復の現在
ーセラミックと接着
ーセラミックインレーの形成
ーセラミックインレーの接着
ーセラミックアンレー〜オーバーレイ形成
ーセラミックアンレー〜オーバーレイの接着
・臨床ケース
【第4回】
1日め
14:15
・保存治療ケースプレゼンテーション前半(一人15分)
16:15
・休憩(15分)
16:30
・保存治療ケースプレゼンテーション後半
18:30
・休憩(10分)
18:40
・熊谷崇先生総括
19:00
・終了
2日め
川勝歯科医院 田中利典先生
9:00~12:00
OPに必要となる基本的な歯内療法について
・病因論、治癒のメカニズム
・問診、口腔内診査、エックス線写真診査
・治療計画、意思決定
・根管形成
13:00~16:00
OPに必要となる基本的な歯内療法について
・根管洗浄
・根管貼薬
・根管充填
・ポストコア、ガッタパーチャの除去
・根管充填後の対応と予後
16:30
・終了
田中利典先生 抄録
一般歯科(保険診療)において、歯内療法は術者の精神的・経済的負担が最も大きい診療分野と言っても過言ではありません。低い保険点数に目を向けてしまうと「一回あたりどれだけの時間でこなすべきか」という考えに囚われてしまい、歯内療法の正しい術式・対処法の考え方が薄れていってしまいます。その結果「短時間で済ませる良い方法はないか」というテクニックだけを追い求めることになりかねません。特に、若い歯科医師においては職場環境によって上記のような治療方針を求められる場合があり、いわゆる「従来の診療スタイル」に染まっていき、いつしか脱却することが極めて難しくなってしまいます。
本講演では、歯内療法の基礎をお話しし、保険診療でも治療効果を最大化する知識と技術をお伝えいたします。OPという医療哲学を実践することと同じく、基本に忠実に歯内治療を実践する環境を整え、1ヶ月後のケースプレゼンテーションに向けて取り組んでいただきたいと思います。
【第5回】
1日め
14:15
・歯内療法ケースプレゼンテーション前半(一人15分)
16:15
・休憩(15分)
16:30
・歯内療法ケースプレゼンテーション後半
18:30
・休憩
18:40
・熊谷崇先生総括
19:00
・終了
19:30
・懇親会開始
21:30
・懇親会終了
2日め
9:00~12:00
・総まとめのケースプレゼンテーション
13:00~16:00
・総まとめのケースプレゼンテーション
・熊谷崇先生総括
16:30
・終了
GOAL
・歯科医療哲学「真の患者利益の追求」←→今の日本の歯科の実態
・MTMの目的・流れの理解
・初診時資料採得の内容・方法の理解
・初期治療時の内容・説明方法の理解
・口腔内写真撮影法の理解・実践(セミナー後の練習法)
・デンタルの位置づけ実践
・クラウドを活用した情報提供
・同じ志をもつ仲間との出会い
費用
¥220,000/人(税込み)
5回分のセミナー受講費および日曜日の昼食代と懇親会費2回分を含みます
※交通費および宿泊費は別途各自でご負担いただきます
入金先
口座名:サット・エクスパンション
三菱UFJ銀行 春日町支店(店番号062)
普通預金
口座番号:0054560
- お振り込み手数料はご負担いただくようお願いします
- 応募は入金をもって確定とさせていただきます
- ご入金いただきその後キャンセルになった場合は、いかなる理由でも返金は致しかねますのであらかじめご了承ください。
定員
10名
参加条件
以下の条件をすべて満たす者
・申込み時点で臨床研修修了後5年以内である
(例)2021年に応募できるのは、2016年度(2017年3月)以降に研修修了した方です
・全5回のすべての日程に参加できる
・セミナー毎の予習(課題図書・論文の読了)と復習(ケースプレゼンテーションの準備)が毎回行える
・ケースプレゼンテーションのための患者の資料採得や治療が行える環境が揃っている
・ケースプレゼンテーションのための患者資料の使用・持ち出しを勤務先院長から許可される
・新型コロナワクチン接種を2回受けていること
・注意事項および備考に了承できる
申込み方法
申込みフォームに入力をお願いします。
申しこみ前に志望動機書(Word形式・1200字)を作成し、申しこみと同時にお送りください
志望動機書のファイル名は「志望動機書(全角スペース)お名前」とし、SAT事務局(info@sat-iso.net)にメールにてお送りください。
選考
先着順ではなく志望動機書により参加者を選考させていただきます
参加の可否は開催1か月前を目処にご連絡差し上げます
持ち物
院内シューズ、実習がある時は白衣、筆記用具
懇親会
第1回め、第5回めに懇親会を行います
会場等については参加者に別途ご連絡致します
交通宿泊手配について
注意事項
- 新型コロナウイルスの感染状況および旅客機の運行状況等により、セミナーを延期する場合があります
- セミナー期間中の録音・録画は一切禁止です
- 配布資料を勤務先以外の者へ開示する行為・SNS等で公開する行為は禁止です
- 参加者が定員に満たない場合(応募者多数だが参加相当と認めた者が定員に満たない場合を含む)はセミナーを開催しない可能性があります